1978年、冬。
2007東京国際映画祭コンペティション部門審査員特別賞受賞
2007ロッテルダム国際映画祭 2007エジンバラ国際映画祭
2007マンハイム・ハイデルベルグ国際映画祭
2007光州国際映画祭 2008フリブール国際映画祭 2008 シンガポール国際映画祭
2008年6月14日(土)より、
渋谷ユーロスペースにてロードショー 全国順次公開

 2002年のベルリン映画祭は、中国映画、あるいはアジア映画を最も精力的に見続けてきた業界人たちでさえ、長らく忘れることのできない想定外の驚愕に震えた年となった。まったく聞いたことのない名前の監督と、誰一人知っているスターさえ出ていないキャスティングによって作られた一本の無名中国映画が、まるで“新人”チャン・イーモウがその監督デビュー作『紅いコーリャン』で87年のベルリンに初登場した時のように、人々に中国からまた一人新しい本物の才能が誕生したことを確信させたからだ。
2002年のベルリン映画祭は、中国映画、あるいはアジア映画を最も精力的に見続けてきた業界人たちでさえ、長らく忘れることのできない想定外の驚愕に震えた年となった。まったく聞いたことのない名前の監督と、誰一人知っているスターさえ出ていないキャスティングによって作られた一本の無名中国映画が、まるで“新人”チャン・イーモウがその監督デビュー作『紅いコーリャン』で87年のベルリンに初登場した時のように、人々に中国からまた一人新しい本物の才能が誕生したことを確信させたからだ。
その作品は『思い出の夏』、そしてそれを監督した主こそ、同作によって監督デビューを遂げたリー・チーシアン(李継賢)だった。そんな彼の、待望の最新作が『1978年、冬。』。完成するなりロッテルダム映画祭を皮切りに各地の国際映画祭で好評を博し、昨秋の東京国際映画祭コンペティション部門ではみごと審査員特別賞に輝いた。
その『1978年、冬。』は、『思い出の夏』と同じく田舎に住む少年が主役の映画。しかしデビュー作が現代の夏を物語の舞台に設定していたのに対し、今回は1978年の冬が舞台となっていることが象徴しているように、映画の雰囲気はデビュー作とは対照的なまでに異なっている。
時代として設定された1978年は、毛沢東の死から2年後。中国が過酷な“冬の季節”、つまり文化大革命時代についに終止符を打ち、いよいよこれから改革開放の時代に踏み出さんとしている時期のことだ。しかしこの映画の少年たちが生活する中国北部の田舎町「西幹道」(本作の中国語原題)一帯は、その凍てついて、不毛で、荒涼とした光景さながら、首都から明るい未来の息吹など押し寄せて来る気配もないまま、永遠に続く冬の時代を過ごしている。
そんな隔絶され、動きを止めた町に暮らす11歳の少年ファントウと、その兄で18歳のスーピンが、この映画の主人公。絵を描くことが趣味のファントウと、いつも工場の勤めをサボっている不良なスーピンの退屈な毎日は、ある日、北京から突然一人の少女が彼らの家の前に引っ越してきたことで、ガラリと様相を変えていく。少女から絵の才能を褒められ、いつの日か展覧会を開くことを夢見るようになるファントウ。片や兄のスーピンは、少女に秘かな恋心を抱きはじめる。肉親から遠く離れて一人孤独にこの町に暮らしはじめた少女も、次第にスーピンと心を通わすようになる。しかしやがてスーピンは、兵役で町から出征。そして一年後、1979年の冬。彼らの誰もが予想しなかった報せが、この町にもたらされる……。
 監督のリー・チーシアンは、1962年生まれの、まさに文革中に少年時代を過ごした世代。映画の中の弟同様、少年時代から絵を描くことを好み、北京電影学院に進んでからも監督科ではなく美術科で学んだ。監督自身、「この映画は、幼い頃の思い出と強く結びついている」、また特に「弟の方には私の投影がある」と述べている。その意味で『1978年、冬。』は、弟ファントウの視点で見た兄とその周囲の世界の物語だと言える。けれど監督は本作を、けっして自己の個人的思い出に耽るようなタッチでは描き出そうとしていない。作中の弟はモノローグすることもなく、寡黙さを貫く。そして彼をとらえるカメラは、むしろ彼からできるだけ距離を置いて、冷徹に、大局的に、事態の推移を見守ろうとしているかのようだ。夏と冬という対極的な雰囲気を各々有する『思い出の夏』と『1978年、冬。』だが、この“引きの視点”とでも呼ぶべきリー・チーシアン美学は両作品に貫徹している。『思い出の夏』を巡るインタビューで、監督は自身の映画論について、「自ら表現しに行ってはならないのです。レンズはむやみに移動せず、それは静観されたものであるべきでした。(中略)私は自分自身も傍観者であり、カメラも同様傍観者であると意識しています」(『思い出の夏』劇場パンフレット所収のインタビューより)と語っているが、それはそのまま『1978年、冬。』の美学を解き明かす。
監督のリー・チーシアンは、1962年生まれの、まさに文革中に少年時代を過ごした世代。映画の中の弟同様、少年時代から絵を描くことを好み、北京電影学院に進んでからも監督科ではなく美術科で学んだ。監督自身、「この映画は、幼い頃の思い出と強く結びついている」、また特に「弟の方には私の投影がある」と述べている。その意味で『1978年、冬。』は、弟ファントウの視点で見た兄とその周囲の世界の物語だと言える。けれど監督は本作を、けっして自己の個人的思い出に耽るようなタッチでは描き出そうとしていない。作中の弟はモノローグすることもなく、寡黙さを貫く。そして彼をとらえるカメラは、むしろ彼からできるだけ距離を置いて、冷徹に、大局的に、事態の推移を見守ろうとしているかのようだ。夏と冬という対極的な雰囲気を各々有する『思い出の夏』と『1978年、冬。』だが、この“引きの視点”とでも呼ぶべきリー・チーシアン美学は両作品に貫徹している。『思い出の夏』を巡るインタビューで、監督は自身の映画論について、「自ら表現しに行ってはならないのです。レンズはむやみに移動せず、それは静観されたものであるべきでした。(中略)私は自分自身も傍観者であり、カメラも同様傍観者であると意識しています」(『思い出の夏』劇場パンフレット所収のインタビューより)と語っているが、それはそのまま『1978年、冬。』の美学を解き明かす。
そんなリー・チーシアン美学をカメラマンとして支えたのは、『ふたりの人魚』『パープル・バタフライ』(以上、ロウ・イエ監督)『呉清源 極みの棋譜』(ティエン・チョアンチョアン監督)などで知られる名撮影監督ワン・ユー。また70年代末の閉ざされ、凍てついた冬の光景を、『硯』(リウ・ピンチエン監督)、『きれいなお母さん』(スン・チョウ監督)の美術監督チュエン・ロンシャーが、その寒さが直接見る者を突き刺すような肌触りでみごとに再現している。 『思い出の夏』でも映画初出演の役者たちを大胆に起用し成功を収めたリー監督だが、『1978年、冬。』の主要出演者たちも、映画初出演、もしくは演技初体験の新人ばかり。彼らから迫真の演技を引き出す監督の演出術も、驚異的というほかない。

 1978年冬、中国北部の小さな町西幹道。通勤と通学の人々を運ぶ通勤列車が、凍てつく空の下をいつものように人々を乗せて走っている。工場に通う人々、学校へ行く子供たち、その土地の人が何かをする時に必ず利用するのがこの名前のない通勤列車である。
1978年冬、中国北部の小さな町西幹道。通勤と通学の人々を運ぶ通勤列車が、凍てつく空の下をいつものように人々を乗せて走っている。工場に通う人々、学校へ行く子供たち、その土地の人が何かをする時に必ず利用するのがこの名前のない通勤列車である。
四角い坊主頭が特徴的で、俯きがちな視線が印象的な男の子ファントウは11歳。近くの西幹道小学校へ通う彼は、内気で人見知りしがちな性格のため、クラスの友達からよくいじめられている。絵を描くのが好きで、授業中も下校後も、時には原っぱのドラム缶を机に、紙がなければ壁を画用紙に、思い浮かぶまま絵を描いている。しかし決して家で描かないのは、父が絵を描くことに反対しているからだ。
彼の父は軍医で無口そのもの、何か問題が起こっても深い眼差しで子供たちを見守っている。反対に母は細かく躾けをし、彼女なりの方法で子供を厳しく管理していた。18歳の兄スーピンは近くの工場に勤めている。仕事をさぼっては廃墟となった背の高いビルにある秘密の場所に隠れ、遠い海外のラジオから流れる知らない言葉で奏でられる音楽を聴いていた。スーピンにとって、ラジオだけが他の広い世界とつながる唯一の窓であったのだ。自分が住む小さな世界を出て遠い世界に憧れる彼は、皆とは違う世界を持っていた。時にそれは勝手気ままに生きているような印象を周囲に与え、母の怒りを買った。ついに兄が工場をさぼっている事が両親に知れ、厳格な母は、弟に兄が工場の門を潜るのを見届けてから学校に行くよう命じた。こうして兄弟二人は、毎朝通勤列車に並んで揺られ、時には線路上を微妙な距離を取りながら歩いて行くこともあった。
そんなある日、家族で見に行った「新年迎戦友文芸演出」という公演で、少女シュエンの踊る姿を見て、兄弟は密かな憧れを抱く。シュエンは北京から来た少女で、兄弟の目の前の家に住んでいた。ファントウは、下校途中でひとり絵を描いている時に通りがかったシュエンに「展覧会が開ける」と言われて舞い上がっていた。
一方のスーピンは、何とか彼女との距離を縮めたい思いであの手この手を駆使するが、却って彼女に誤解されてしまう始末だった。しかし、思いがけない事件により誤解を解くことに成功し、二人はスーピンの秘密の場所で一緒に時間を過ごすようになるが、いつしかスーピンとシュエンの仲が町の噂になってしまい、それが原因でファントウがいじめられる事態にまで発展してしまう。結局、スーピンは自分の素行のせいでいじめられる弟を見かねて、家を出て軍隊に入隊することを決意するが――。
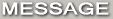
人生の多くの時間は孤独だがエネルギーに溢れています。それが愛です。
監督:リー・チーシアン(李継賢)
この映画は、幼い頃の思い出と強く結びついています。小さな頃、軍人の父と一緒に東北、河南、湖北地方などで暮らしました。かつての思い出は記憶の中にしっかりと残されているか、紙に描かれて残っています。質素な時代でした。父は農村出身から兵隊になった人で、寡黙な人でした。いつもその眼差しは静かな馬のようで、変わることがありませんでした。父の着る、洗った白い軍服は、深く冷たい井戸水の雰囲気を残し持っているようでした。母も農村出身で、声が大きく、かんしゃく持ちで口が悪い。子供たちの躾が出来ません。兄は荒野を駆け回る野うさぎのように手が付けられませんでした。
あの頃は、中国の特別な時代でした。物がなく、映画の中の、閉ざされた小さな町の厳しい冬のようでした。雪に覆われた広野を見渡すと、遠くにコンクリート工場、鉄工場、カーバイト工場の音がする。通勤の列車は日々この町の周りを走る。通学の子どもたち、通勤の労働者たちは皆それに乗り、日々生活は繰り返される。閉ざされた町の人々は外の世界を知らないのです。
今日の中国における大きな発展により、状況は大きく違ってきました。人々の意識さえも変わって来ていると思います。
私はこの変化に注目しました。そのためこの映画の映像は静止しているか、あるいは平静でさえあります。荒涼さと力の質感が、ある種の自然で原始的な雰囲気を創りだししています。
人の感情表現はそれほどまでに直接的で質素、自然なものなのです。
30年前の経験は、私の人生と共に時を経てきました。それは今日の大きく発展する中国、世界的な規模を背景にしています。私は、精神的な世界にこそ、かつて初めて感じた<本質>がある事を、今も忘れないでいます。この作品が、世界中の異なる文化的背景を持つ観客に、大きな共感を呼び起こす事を期待しています。
それが正に映画の素晴らしさのひとつだと思っています。

2007年東京国際映画祭 ティーチ・イン&記者会見
Q:本当に素晴らしい繊細な作品です。主役は弟の小さい子供の方だと思います。この男の子は監督の少年時代と考えてよろしいのでしょうか。
監督「おっしゃる通りです。この登場人物の全てにモデルがいます。ただストーリーは私たちが創作したものです。私自身も子供の頃絵を書いていましたので、弟の方には私の投影があると思います。弟の、子供の目を通して描いた世界、ということになります。」
Q:東京国際映画祭に関して感じたことをお聞かせ下さい。
監督「東京は2度目なのですが、とてもいい印象を持っています。毎回思うのは、空港から来ると段々建物が増えてきますよね。その現代的で整然とした様子が、民族の特徴を感じさせます。そして道路を走っていてもとても静かです。映画祭の印象ですが、今回何本か作品を見ました。他の映画祭では見ないような個性ある独特の作品が見られると思いました。」
沈佳妮「一昨々日に着いて、一昨日は仕事をして、昨日東京でショッピングをしました。東京は女の子にとっては買い物天国です。日本の方はとてもやさしくて、昨日ネックレスを買ったら、今手にしているブレスレットをくれました。うれしかったです。今回国際映画祭初めての参加です。中国では学生映画祭等に参加したことがあります。この映画祭は今回20回目ということできちんといろいろなスケジュールが出来ていて、私たちへの気配りも出来ています。心配もなくスムーズに進行していて関心しました。」
李薇(脚本)「初めて東京に来ました。毎日おいしいものばかり食べていて太ってしまいそうです。ビルの間に小さな日本家屋があり、それがとても日本情緒を感じさせました。映画祭はヨーロッパやアメリカに行ったことがあります。それぞれ特徴がありますが、組織がシステマティックにしている。私たちの映画をコンペ部門に選んで下さったということも、この映画祭の特色があると思います。コンペのほかの作品も何作か見ましたが、それぞれ突出したいいものを持っていて、まるで映画の勉強をしているような気持ちです。観客としても製作者としてもいい機会を与えてくださっていると思っています。今後も監督とともにいい作品、新しい作品を作れるように頑張って行きたいと思っています。」
Q:この作品の企画は10年以上前からあると聞いています。ここまでのいきさつをお教えください。
監督「おっしゃるとおりです。私の心の中で10数年暖めてきた映画です。学生時代、1994年にこの構想がありました。その頃脚本家のリー・ウェイに会いました。現在の僕の妻ですが、当時はまだ北京大学の学生でした。彼女を誘い出す口実として、ちょっと書いたものがあるんだけど見てくれないか、といって誘いました。ひと晩かけてこの物語を話すと彼女は涙を流してくれました。それから長い時間をかけて脚本を作っていったのですが、今でも覚えているのは、大学のキャンパスの中で果実のなる下で、石のベンチに座って、当時はパソコンがなかったのでお互いペンを使ってこの脚本を書きました。この映画のように非常に寒い時期だったので、魔法瓶とコップを持って。貧しい僕たちがずっと暖めてきた作品です。インクが段々一つの印刷物になるように、この映画が出来上がりました。その間中国自身も非常に大きく変わりましたし、僕たち自身もいろいろ勉強して変わりました。でも最初の書きたいという構想、信念というのは、どんな困難にぶつかっても変わらずにいました。」
Q:カメラが引いて撮影しているのは、何か演出的な意図があったのでしょうか?
監督「この映画の舞台背景は1978年です。これは中国では丁度文化大革命が終わっていて、改革開放の時代がまだこれから、という空白の時代です。この時代をどう描こうか、切り口として、人々がまだこれから世の中がどうなるか解らないという状況の下での、ある地方の小さな町をある家庭を元にして描こうと思いました。その時代のある人々の運命であるとか、孤独と愛を求める気持ちを描こうとした。長回しのカメラで撮ったのは、この映画は実は私自身の子供時代の記憶と関係があります。今この年になって子供の時代を振り返る、その貴重な時代とそれから今までの長い長い時間、誰しもそうでしょうが、その人生の道のりを見たいということ。さらにこれは子供の目から見た大人の世界です。まったく白紙の状態から見ていて、障害も汚れたものもない。それをどう表現したらいいのかと考えた時に、また主人公たちの内心の感情をどう表現したらいいか、という時に、脚本とも話しをしまして、主人公たちが歩いているシーンも、まるで動物の記録映画を撮るような、自然の中に主人公たちをそっと置いて、そうすることでささやかな命の尊さであるとか、ありふれた人生を描けるのではないか、という理由です。監督の演出というよりも、自分の見て欲しいものを映し出した、ということです。」「編集方法もそれにあったものを使用しています。すべてがシンプルで力強い物語に従属しています。ロケ先もそうです。山西省のチャンチー県という所で撮りました。非常に独特の風景のところです。それが非常にまたこの物語にあっていると思っています」
Q:実際ご自身はもともと踊りと楽器を勉強していたのですか?
沈佳妮「ダンスは中央戯劇学院に入るまえに、新体操をプロとしてやっていたので、基礎はありました。踊りそのものは撮影が始まってから現場でやったのですが、あまり問題ありませんでした。まったく音楽の才能は無いのですが、2004年にアジアンオリンピック、2008年にオリンピックが開かれるということで、出し物として4人の女の子が選ばれて、それぞれが中国の伝統楽器を弾くというのがありまして、ジャスミンの花という曲を演奏しました。私は二胡担当に選ばれて、2ヶ月間集中訓練を受けました。実際引くことは出来ないのですが、見た目は結構様になっていたと思っています」
Q:芝居でかなり苦労があったと思います。監督からの具体的な指示等ありましたら教えてください。
沈佳妮「監督が言ったのは、何でも縁だよね、ということです。私も監督と縁を感じました。現実はなかなか言葉では説明できず、時々自分で感じるということが必要だと思います。監督はよく大まかなシチュエーションを話して、大体こういう感じ、解った?って言うんです。でも私は感覚で解りました。言葉では説明できないことを監督との間で感じることが出来ました。今までこのような芸術映画に出たことがなく、これは完全に芸術映画だと思うのですが、純粋な芸術映画に出たかったのでとても期待していました。演技も今までとは違っていました。監督はずっと遠くにいて、そこに座っていたり立っていたりしました。かなりの時間の間に、その時の役の本当の気持ちをその場で出さなければいけないという、そんな経験をしました。」
Q:映画化までになぜこのような時間がかかったんでしょうか
監督「そもそもこのストーリーが浮かんだ段階では監督をしていませんでした。その頃電影学院で美術をやっていたのですが、3年生の頃から真っ白なキャンパスに絵を描く様にスクリーンにもそういうようにして映画を作れるのではないかと思っていました。段々自分でも脚本を書くようになり、友達にも見せて知らせたのですが、なかなか監督をする機会に恵まれませんでした。映画美術の仕事をしていましたし、脚本家(リー・ウェイ)はまだ学生でした。毎朝起きると、アドレス帳を見て誰だったらお金を持っているか、誰だったらプロデューサーに知り合いがいるとか、その人に晩御飯でもご馳走したら、そんな機会がつかめるだろうかとかそんなことを考えていました。そうこうしているうちに、ある有名な監督さんがやってごらんと高評をしてくれて、自分でもやることが出来るかもしれないと思いました。でも2回ほど、今度こそ撮影できるという段階で、いろいろな原因で撮影できなかったということがありました。」
李薇「人生はなぜといわれても答えが出ないものだと思います。20年探し続けても最愛の人に巡りあえない人もいれば、わずか数秒で最愛の人にめぐり合ってしまう人もいて、それはまさに運だと思います。これこそ東洋の哲学であり、仏教の無常観とも関係するのでしょうか、ですが、そういう機会が巡ってきたなら、もし無くても自分の運命を受け入れて、自分のすべきことを淡々とすること、自分の夢を持ち続けることが大事だと思います。13年間かけてこの作品を撮ること、それを3ヶ月で撮ってしまうということ、それはあまり重要ではないと思います。」
Q:線路脇にある木が印象的ですね。
監督「線路の脇にある木がどんな種類なのかは分からないのですが、中国北部の厳しく乾いた環境で育つ種類のはずです。その上、成長の度合いが極めて低いから映像の中では際立って大切なものと映ります。この木は人が植えたのではなく、自分で生えてきたのだと思います。風に運ばれた種が田んぼの水を吸って成長し、荒野の四季の寒さ、雨風と太陽のぬくもりを受けてきました。この映画のテーマ、人の運命と象徴的な関係にある。孤独や漂流、運命の無常。しかし自然界の生命力は偉大だと思います。
ロケ地を選ぶ時、この木を非常に気に入りました。私は美術スタッフに「西干道」の看板をここに立てさせ、印象的な構図としました。木と看板は互いにシンボルのように映し出されます。2つの美しさがここで起きた事を思い起こさせますね。」
Q:通勤列車について教えてください。
監督「まずは「西干道」という名前について説明します。「西干道」は地名です。この呼び名に中国の小さな町の特徴が現れています。現地の人々はこの辺りの鉄道を「西干道」と呼び、20里離れた所では「東干道」、「北干道」などと呼ばれているかもしれません。また別の所では線路のこちらとあちらと呼ばれます。例えば、道のこっちは西干道、あっちは東干道などというように。ファントウ、スーピンが乗る列車は「通勤列車」です。「通勤列車」とは何か。“通”は交通の意味、“勤”は出勤するということ。つまり工場へ行く専用列車、一般的に下層の労働者たちが通勤時に乗る列車のことです。こうした列車は無料で各駅に止まり、近隣の人々の生活とは切っても切れない関係にあります。当時、小さな町には基本的にバスなどの交通手段はなく、子供たちの通学、大人が親戚の家へ行く、生活用品を買いに行く時などは皆このような列車に乗りました。通勤列車は現地の人の生活と外界を結ぶ唯一の交通手段でした。
このような通勤列車に決まった名称はなく、ただ通勤列車と呼ばれています。通勤列車といえば現地の人は皆分かるんです。現在の交通機関である地下鉄、タクシーなどとは違いますね。『西干道』の中の通勤列車は当時の様子を表しています。美術のチュエン・ロンシャーは電影学院に通う前は、東北地方で毎日この電車に乗っていました。彼の設計した列車は貨車と客車がつながれています。貨車は主に小さな店に荷物を運んでいます。肉や油といった食料や柴などです。客車は人用だったが貨車を改造したものでした。(当時の通勤列車では人用の客車は貨車を改造したものだった)。これは非常に忠実な再現です。映画に登場する列車は美術スタッフが手を加えたもので、上にはカメラマンがライトを置く場所がついています。『西干道』の通勤列車と映画のテーマには密接な関係があります。列車のアナウンスにあるように「通勤列車は街を周っています。通勤の人も通学の人も皆これに乗って・・・」これは当時の中国の閉ざされた町の縮図です。映画の中の登場人物の運命はそれぞれに変化と無常があります。死んでいく者、離れる者、永遠に残る者。しかし、生活は依然として変わりません。毎日町を周る列車のように・・・。」

STAFF
エグゼクティブ・プロデューサー:ヤン・プーティン(楊歩亭)/ 多井久晃
プロデューサー:ハン・サンピン(韓三平)/ 鈴木一
ライン・プロデューサー:チャオ・ハイチャン(趙海城)/ 仲偉江
脚本: リー・チーシアン(李継賢)/ リー・ウェイ(李薇)
監督: リー・チーシアン(李継賢)
撮影: ワン・ユー(王昱) 美術: チュエン・ロンシャー(全榮哲) 録音: リー・シュエレイ(李学雷)
CAST
ファントウ(方頭):チャン・トンファン(張登峰) スーピン(四平):リー・チエ(李傑)
シュエン(雪雁):シェン・チア二ー(沈佳妮)
ファントウのお母さん:チャオ・ハイイエン(趙海燕) ファントウのお父さん:ヤン・シンピン(楊新平)
2007年/中国・日本/中国語/35mm/カラー/1:1.85/ドルビーSR/101分
原題:西干道/英題:The Western Trunk Line/日本語字幕:田村祥子、大村緑
製作:中国電影集団/株式会社ワコー 配給:ワコー/グアパ・グアポ
配給協力:フォーカスピクチャーズ 宣伝:グアパ・グアポ 宣伝協力:テレザ 協力:マルマン株式会社
後援:中華人民共和国駐日本国大使館文化部
http://www.1978-winter.com/
(C)2007 China Film Group Corporation & Wako Company Limited.
2008年6月14日(土)より、
渋谷ユーロスペースにてロードショー 全国順次公開

紅いコーリャン
amazon.co.jpで詳細をみる

ふたりの人魚
amazon.co.jpで詳細をみる

パープル・バタフライ
amazon.co.jpで詳細をみる

きれいなおかあさん
amazon.co.jpで詳細をみる
TRACKBACK URL:

