ベンジャミン・バトン
数奇な人生
2009年2月7日(土)より、丸の内ピカデリー他全国ロードショー

80歳で生まれ、若返っていく
数奇な人生を生きた、ある男の物語
 私は数奇な人生のもとに生まれた――。「グレート・ギャツビー」で知られるF・スコット・フィッツジェラルドが、1920年代に書いた短編を基にした『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』は、こうして幕を開ける。それは80歳で生まれ、年をとるごとに若返っていく男の物語。ほかの人々と同じように、彼にも時を止めることはできない。
私は数奇な人生のもとに生まれた――。「グレート・ギャツビー」で知られるF・スコット・フィッツジェラルドが、1920年代に書いた短編を基にした『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』は、こうして幕を開ける。それは80歳で生まれ、年をとるごとに若返っていく男の物語。ほかの人々と同じように、彼にも時を止めることはできない。
第一次世界大戦末期の1918年にニューオーリンズで始まり、21世紀へと続く彼の人生は、たとえようもないほど不思議なもの。“普通”とは言い難い彼は、出会った人々や場所を心に刻み、愛と出会い、愛を失い、生の喜びと死の悲しみに震えながら、壮大な旅を続ける。
生まれてすぐに捨てられたベンジャミンに、無償の愛をくれた育ての母。外の世界へ飛び出し、誘われるまま乗った船で仕事をくれた船長は「自分の信じる道を進め」と教えてくれた。異国で出会った女性との初めての恋、初めてのくちづけ。第二次世界大戦で共に戦い、夢半ばで散った男たちと結んだ絆、名乗り出た実の父の死……ベンジャミンは自分に与えられたさまざまな機会をすべて受け入れ、そこで出会った人々と深くかかわっていくことに、生きる意味を見出していく。
そんな数え切れない出会いと別れの中で、ベンジャミンの人生を大きく変えたのは、生涯思い続けた女性、デイジーだ。互いに求め合いながらも、別々の時の流れを生きなければならないふたり。人生のちょうど真ん中で、やっとほぼ同じ年齢になったふたりは、互いを慈しむように強く優しく愛し合う。しかし、彼らは気づいていた。やがてまた、時に引き裂かれることを――そのとき、ふたりが選んだ人生とは?この世に、時を超えて残る愛は、あるのだろうか――。
ベンジャミンは知っていた。出会った人々と、いつか必ず別れることを。だからこそ、この一瞬一瞬を大切に生きたい――『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』は、特別な運命を生き抜いたベンジャミンの曇りなき瞳を通して、人生の素晴らしさを見せてくれる感動作である。
ブラッド・ピット×ケイト・ブランシェット×デビッド・フィンチャー
ハリウッドだけが叶えられる、夢の組み合わせ
 ベンジャミン・バトンを演じるのは、世界中で圧倒的な人気を誇るブラッド・ピット
ベンジャミン・バトンを演じるのは、世界中で圧倒的な人気を誇るブラッド・ピット。その輝かしいキャリアの中で、アクション、コメディ、ラブストーリー、感動作と、すべてのジャンルの役柄を完璧に演じてきたピットが、今度は年々若返っていくという誰も演じたことのない役どころに挑んだ。ベンジャミンの生涯の恋人であるデイジーには、鍛え抜かれた演技力と磨き上げられた美貌で、常に観客を魅了するアカデミー賞女優、ケイト・ブランシェット
。
監督は、『セブン』『ファイト・クラブ
』のデビッド・フィンチャー
。今の時代を代表するのはもちろん、未来の映画界を担う監督のひとりだ。本作では、フィンチャー監督が得意とする前代未聞の設定を入口にしながら、登場人物一人ひとりの体験を丹念に描き、観る人すべてが「これは自分の物語だ」と感じられるストーリーを紡ぎ出した。観終わった後に誰もが自分の人生について話したくなる感動作に、早くも全米マスコミの多大なる注目が集まっている。賞レースの口火を切るナショナル・ボード・オブ・レビューでは監督賞を受賞、作品ベスト10にも選ばれた。批評家たちは、この勢いはオスカーまで続くと絶賛の声を惜しまない。
一生に一本の一級品を支える、一流のスタッフ・キャストたち
拾った赤ん坊にベンジャミンと名づけて、我が子同然に深い愛を注ぎ続けるクイニーには、『スモーキン・エース/暗殺者がいっぱい』のタラジ・P・ヘンソン。デイジーの一人娘キャロラインには、『レジェンド・オブ・フォール 果てしなき想い
』のジュリア・オーモンド
。ベンジャミンを捨てたことを悔やみ続ける父トーマスには、『スナッチ
』のジェイソン・フレミング
。ベンジャミンが初めて恋におちる女性エリザベスには、『フィクサー
』でアカデミー賞助演女優賞を獲得したティルダ・スウィントン
。
脚本は、『フォレスト・ガンプ/一期一会』でアカデミー賞を受賞したエリック・ロス
。世界大戦など歴史のダイナミックな流れを時代背景に、人々の日々の営みの細部を描き出す才能を、本作でも存分に発揮している。気品溢れる音楽は『ライラの冒険 黄金の羅針盤
』のアレクサンドル・デプラ。独創的な照明を駆使し、観る者の心に詩的な余韻を残す映像を手掛けたのは、クラウディオ・ミランダ。フィンチャー監督の『ゲーム
』『ファイト・クラブ
』では照明係を務め、今最も注目されている撮影監督だ。
2009年、一生に一度の出会いを、贈ります。

 人生は素晴らしい――
人生は素晴らしい――
「私はベンジャミン・バトン。変わった境遇で生まれてきた。第一次世界大戦も終わり、生まれるには最高の夜だった――」
1918年、ニューオーリンズ。黒人女性クイニー(タラジ・P・ヘンソン)は、置き去りにされた赤ん坊を拾う。ベンジャミンと名づけられたその男の子は、すぐにクイニーが営む施設の老人たちの中に溶け込んだ。なぜなら彼は、80歳で生まれてきたからだ……。
“母親”クイニーの惜しみない愛情に包まれて、ベンジャミン(ブラッド・ピット)は成長していった。車椅子から立ち上がって歩き出し、しわが減り、髪が増え……そう、ベンジャミンは日に日に若返っていったのだ。
1930年、感謝祭。その日、ベンジャミンは、将来自分の人生を変えることになる少女と出会う。施設の入居者のフラー夫人を訪ねてきた孫娘、6歳のデイジーだ。ふたりはすぐに心を通わせ、ベンジャミンは自分の秘密を打ち明けるが、デイジーはそのことを既に魂で感じていた。
ある日、ベンジャミンは働かないかと誘われてマイク船長(ジャレッド・ハリス)の船に乗り、さまざまな“初めて”を体験する。海、労働、女性、帰り道に声をかけられた男と飲んだ酒。男の名はトーマス・バトン(ジェイソン・フレミング
)、ボタン製造会社のオーナーだ。実は彼こそが、ベンジャミンを捨てた父親だった。出産直後に亡くなった妻との、息子を守るという約束を果たせず、後悔の日々を送っていた。
1936年、ベンジャミンは皆に別れを告げ、デイジーには「どこへ行っても葉書を出す」と約束して、再び海へ出る。やがて、英国のスパイの妻であるエリザベス・アボット(ティルダ・スウィントン)と恋におち、男として愛される幸せを知る。だが、その恋は短命だった。 1941年、太平洋戦争が始まり、エリザベスは消え、ベンジャミンの船は戦争に駆り出される。
1945年、戦いで大切な友を亡くしたベンジャミンは家に帰り、すっかり美しく成長したデイジー(ケイト・ブランシェット)と再会する。彼女は、ニューヨークでモダン・バレエのダンサーとして活躍していた。心の片隅では、いつもベンジャミンを思いながらも、若きデイジーはまだ、自分だけの人生に夢中だった。ふたりはまた、別々の時を進む。
ベンジャミンと再会したトーマスは、遂に自分が父親だと打ち明ける。不治の病で余命わずかのトーマスは、ベンジャミンの母との幸せな出会いを語り、ボタン工場や屋敷など全財産を譲りたいと申し出るが、ベンジャミンは「僕の家に帰る」と静かに立ち去る。それでもベンジャミンは、父の最期の日々にそっと寄り添うのだった。
1962年、喜びも悲しみも、孤独も知った人生のちょうど真ん中で、遂にほぼ同じ年齢を迎えたふたりは結ばれる。愛に満ちた幸せな日々の中で、ふたりは恐れ始める。やがてまた、時に引き裂かれることを。日に日に若返るベンジャミンは、ある決意をするのだが……。
果たしてふたりは、求め続けた“永遠”~時を超える愛~を、見つけることができるのか――?
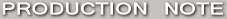
 本作の基になっているのは、1920年代に書かれたF・スコット・フィッツジェラルドの短編小説。フィッツジェラルド自身はマーク・トウェインによる、「もし、人が80歳で生まれ、ゆっくりと18歳に近づいていけたなら、人生は限りなく幸福なものになるだろうに」という言葉にインスピレーションを受けた。
本作の基になっているのは、1920年代に書かれたF・スコット・フィッツジェラルドの短編小説。フィッツジェラルド自身はマーク・トウェインによる、「もし、人が80歳で生まれ、ゆっくりと18歳に近づいていけたなら、人生は限りなく幸福なものになるだろうに」という言葉にインスピレーションを受けた。
フィッツジェラルドの短編はとても風変わりだったため、その映画化は、あまりにも野心的、あまりにも空想的で実現は難しいと長い間思われていた。そして、このプロジェクトは40年以上、宙に浮いた形になっていたが、そんなときにプロデューサーのキャスリーン・ケネディとフランク・マーシャルの目に留まった。また、エリック・ロス、デビッド・フィンチャー
、そしてブラッド・ピット
も同じように、10年以上もこのプロジェクトを気にしていた。
ロスにとって、このプロジェクトのコンセプトは、毎日の一瞬一瞬の密な体験、世界大戦のような大きな経験から、キスのようなちょっとした経験まで、あらゆる出来事を通して、人生という大きなカンバスを内省的に見てみる機会となった。「このような壮大でありながらも、心の奥を深く描くストーリーの可能性を最大限に生かす脚本家としては、エリックはまさに理想的だった」とケネディは言う。「彼は『フォレスト・ガンプ/一期一会』の脚本で、歴史的な時代背景を舞台にした親密で個人的な描写をものにし、細部まで豊かに描く才能を見せつけたわ」
人生を逆向きに生きるチャンスというものは理想的に思える。「でも、そんなに単純なことではないんだ」とロスは言う。「それは一見、すばらしいことに思えるかもしれないが、それは別の種類の人生になり、そこがこのストーリーのすばらしさだと私は思う。ベンジャミンは若返って生きていくとはいえ、ファースト・キスや初恋は普通の人生で経験するのと同じように彼にとって重要な意味をもつ。逆向きに生きようが、普通に生きようが、結局は変わらないんだ。大事なのはどう生きるかということなんだよ」
本作のストーリーの構想を練り、脚本を書いている間に、ロスは両親を亡くした。「両親の死は、私にとってもちろんとてもつらいものだったし、それによって、物事に対して違う見方をするようにもなった」とロスは思い返す。「このストーリーでは、私の心に響いた同じ部分に人々も反応するんじゃないかな」
この映画が探っていくのは、時代と年齢を超えたところに存在するもの――人生の喜び、愛、そして喪失の悲しみ――である。「デビッドと私は、これが自分のストーリーでもあり得ると観る人すべてに感じてほしいと思った」とロスは言う。「結局、これはひとりの男の人生なんだよ。そこがこの映画の特別なところであり、同時に、とても普通のことでもあるんだ。ベンジャミンに影響を及ぼすものは、どんな人にも影響を及ぼす」
ベンジャミンの状況は完全に特異であるものの、彼の旅が浮き彫りにしていくのは、どの人間の人生の芯の部分にも存在する複雑な感情だ。「私たちは生きていくうえで、さまざまなことを自問する。このストーリーはそこを突いてくる」とマーシャルは言う。「1本の映画で、これほどさまざまな個人的な視点を引き出す作品はめったにない。60代や70代の人々の見方と、20代の人の見方は違うはずだしね」
製作のシーアン・チャフィンは、このプロジェクトが長い間、フィンチャーの頭から離れず、いったん消えても、また戻ってきたことを覚えている。92年にチャフィンがデビッドのもとで働き始めたときに、初期の段階の脚本はすでに彼のデスクにあった。「彼はそれをとても気に入っていて、長年の間に何度も検討し直していた」と彼女は言う。「それに、ブラッドがこの脚本についてデビッドに尋ねたのも覚えてる。デビッドは、『すばらしい映画になる可能性がある』と答えてたわね。脚本というものは、なかなか手元に留まらないもの。でも、この脚本は決して完全にデビッドのもとから離れることはなかった。彼は、去っていくものにはそれなりの理由があり、それを悔やんでも仕方がないといつも言っているの。つまり、この脚本は留まるだけの理由があったということよね」
フィンチャーは、愛する人を失った自分の体験により、このストーリーにますます惹かれた。「僕の父は5年前に亡くなったんだが、父が最後の息をした瞬間が忘れられない」と彼は言う。「あれはものすごく深い体験だった。多くの意味で自分を人間として成長させてくれた人、自分のほんとうの目標だった人を失うのは、人生のバロメーターを失うに等しい。もう誰かを喜ばそうとしなくなり、何かに反応することもなくなる。多くの意味で、ほんとうに独りぼっちになるんだ」
まだ準備期間の初期のころ、ケネディ、マーシャルとの打ち合わせが、いつの間にか、かなり個人的な打ち明け話になることが多かったとフィンチャーは思い返す。「ストーリーについて話し合い始めて15分も経つと、みんな、自分に実際に起こった話をしていたんだ。亡くなってしまった愛する人、こっちはとても好きだったのに、注意を払ってくれなかった人、自分が追いかけた人、自分を追いかけた人……そんな人たちの話をした。そこがこのストーリーの不思議なところで、誰もがそういう話をしたくなる」
 このストーリーの映画化は、ドラマチックな面だけでなく、技術的にも難易度が高く、大胆なアイデアだと思われた。「たった1本の映画の中で、揺りかごから墓場まで、山や谷にあふれたひとつの人生をどうやって巧妙かつ簡潔に創り出せる?」とケネディは考え込む。「エリックの脚本では、それぞれの瞬間に生まれる感情が、あとになって心に響いてくるの。どこかをごまかそうとすれば、そのすばらしい体験が弱まってしまう。だから、人生全体を創り出すには時間がかかると最初から覚悟していたわ」
このストーリーの映画化は、ドラマチックな面だけでなく、技術的にも難易度が高く、大胆なアイデアだと思われた。「たった1本の映画の中で、揺りかごから墓場まで、山や谷にあふれたひとつの人生をどうやって巧妙かつ簡潔に創り出せる?」とケネディは考え込む。「エリックの脚本では、それぞれの瞬間に生まれる感情が、あとになって心に響いてくるの。どこかをごまかそうとすれば、そのすばらしい体験が弱まってしまう。だから、人生全体を創り出すには時間がかかると最初から覚悟していたわ」
ピットにとって、ベンジャミンを演じる唯一の方法はすべてを、どの年齢の彼をも自分で演じることだった。それはもちろん、制作上でもっとも大きなチャレンジのひとつとなった。「ブラッドは、ベンジャミンの生涯を通して完全に演じられなきゃやらないと言ったんだ」とフィンチャーは言う。「キャサリンとフランクは、どんな方法でそれを実現させるのかに興味津々だったな。僕は、『分からないけど、なんとか考える』と言っておいたよ」
ピットもベンジャミンの生き方に深く惹きつけられた。「そのキャラクターがどんなことをやれるのかを、役を引き受ける判断基準にする俳優が多い」とフィンチャーは言う。「ベンジャミンは物理的に多くのことを“する”わけではないが、彼が経験することといったら、いや、もうすごいよ。この役にはブラッドはピッタリだった。彼レベルの俳優でなければ、弱くなってしまうタイプの役なんだ」
ピットの相手役にフィンチャーが起用したのはケイト・ブランシェット。彼は、『エリザベス
』でブランシェットの演技を観て以来、彼女が頭から離れなかった。「映画館で、『あの女優は誰だ?すごい』と思いながら観てたのを覚えているよ」とフィンチャーは思い返す。「あれだけのパワーと能力の持ち主にはそうそうお目にかかれない」
「ケイトのおかげで、僕たち全員の演技の質が高まった」とピットは言う。「彼女はほんとにすばらしい。とてもいい友人でもある。彼女ほど洞察力の深い女優はあまりいないよ。僕は彼女を優雅さの権化だと思ってるんだ。彼女のダンサー役はとてもいいよ。彼女の人柄や内面の優雅さがデイジー役にピッタリはまってる」
デイジーとベンジャミンの関係は、彼女が彼の尋常ではない状況を理解し、それを受け入れていくようになるにつれ、発展していく。それについて、ロスはこう語る。「ケイトはデイジーを見事に表現している。デイジーは、自分が年をとっていくのに、愛する人は逆に若返っていくという事実を受け入れなければならない。そしてそれを受け入れたとき、彼女の人生はどうなる?彼女は最初はせっかちで、情熱的な若いダンサーだが、やがて強さを内に秘めた大人の女性に成長していくんだ」
ブランシェットは、少女時代に習っていたバレエを生かして、ダンサーとしてのデイジーの姿勢と情熱を形作っていった。「私は子供のころ、女の子が興味をもつことをいろいろやっていて、バレエも習ったけど、ピアノかバレエかどちらかを選ばなければならなくなったの」とブランシェットは説明する。「それでピアノを選んだんだけど、結局、ピアノもやめて演技の勉強を始めたのよ。私はダンスがとても好きだけど、自分の限界は知ってるの。今回、またあの大好きな世界へ行けて、とてもうれしかったわ」
デイジーはベンジャミンの人生にかかわってくる多くの人々のひとりだ。「ベンジャミンはビリヤードの突き球みたいなもの。そして、彼が遭遇する人々すべてが彼に何らかの痕跡を残していく」とフィンチャーは説明する。「それが人生というものなんだよ。ほかの人や出来事に遭遇することでできる“へこみ”や引っ掻き傷の集合体が人生なんだ。それによって、ほかの何者でもないベンジャミンという男が出来上がった」
「僕はこの“へこみや傷”というアイデアが気に入っている」とピットは言う。「人は出会った相手に何らかのインパクトを与え、印象を残していく。そこには、どこかとても詩的で、受容的な雰囲気がある。それは別に投げ出すわけではないよ。自分が求める何かのために頑張るのをやめるということでもない。人生の必然性を受け入れるということなんだ。人は僕らの人生に入ってきては去っていく。人は去るものなんだ。それが選択によってであろうと、死によってであろうとね。自分自身がいつかは去るように、人は去っていく。それが必然性というものだ。それとどう向き合うかが問題になってくる」
ピットはこの考え方を友人でもある監督と共有している。「この映画が掘り下げていくのは、人は自分自身の生き方に責任があるという信念で、それはデビッド自身の考え方でもある」と彼は言う。「僕たちは自分の成功にも失敗にも責任があり、ほかの誰かのせいにするべきではないし、誰かに功績を渡してしまう必要もない。運命もある程度は関係するけれど、結局のところ、その結果をもたらしたのは自分自身なんだ」
ベンジャミン役はピットにとって、生涯を通して出会う人々に反応しながら、精神的な成長を表現するという点で、これまでの映画では経験したことのないような複雑なチャレンジとなった。「ベンジャミンの旅はとても内省的なものなの」とブランシェットは言う。「はっきり目に見える肉体の変化を表現するというのは俳優として当然、難しいことだけど、それよりも、じっと観察し、存在感があり、出会う人一人ひとりと深くかかわっていく人物を演じることは大変なものよ」
「これはおそらく、ブラッドの俳優人生でもっとも静かな演技だと思う」とフィンチャーも付け加える。
ロスは、ピットがもともともっている人間性によって、ベンジャミンがもつ特異な側面でさえ、自然に見せたと指摘する。「ブラッドがベンジャミンをいわゆる“普通の男”として演じきったところがすごい。おそらくブラッドは、実際にベンジャミンに共感する部分があって、それが“ある役を演じる”という枠を超えさせてるんじゃないかな。彼は、人とは違う人生を歩むということがどんな感じか、理解しているんだよ」
 ベンジャミンの養母クイニーは彼の生涯を通してこう語りかける。「人生に何が待っているかなんて誰にも分からないものよ」
ベンジャミンの養母クイニーは彼の生涯を通してこう語りかける。「人生に何が待っているかなんて誰にも分からないものよ」
ベンジャミンは1918年、第一次世界大戦終結のニュースで沸くニューオーリンズで生まれた。普通なら、いい夜に生まれたと言えよう。彼の母は出産で命を落とし、父は息子の姿に恐れおののき、生まれたばかりの息子を、ノーラン・ハウスという老人ホームの階段に置き去りにしてしまう。そこでベンジャミンは、ホームを仕切っているクイニーに引き取られる。
タラジ・P・ヘンソンは、実は、このプロジェクトがまとまるかなり前からクイニー役を射止めていた。フィンチャーのキャスティング・ディレクターであるラレイ・メイフィールドが、『ハッスル&フロウ』での彼女の演技を見るようにフィンチャーをさりげなく誘導したからだ。「タラジのエネルギーと母性にみんな、圧倒されたんだ」とフィンチャーは思い返す。「クイニーがもつ温かさ、人を外見で判断しない資質などすべてをタラジはもっていた」
クイニーは、多くの人が生涯かかってもできないような仕事をしている。「クイニーは死にどう向き合えばいいかを知っているの」とヘンソンは言う。「それと同時に、彼女は無条件の愛にあふれた女性。人種差別が一般的だった時代に白人で、しかも普通ではない状態で生まれてきた子供を引き取る彼女は、そういう外見的な違いはまったく意に介さず、彼を愛することができるの」
クイニーという人物はとても個人的なレベルでヘンソンに訴えかけてきた。「この役を演じるのは私にとって、とても精神的な意味が大きかった」と彼女は打ち明ける。「当時、私は父を亡くしたばかりだったの。私は父を心から恋しく思っていたし、父が予測していたとおりに私が生きていく様子をそばで見守ってほしかったけど、まるで父の死は私がクイニーに近づく旅の一部のように感じられた。父が病気のとき、私たち家族は父を決して独りぼっちにしないと誓ったの。だから、いつも誰かが父のベッドのそばにいた。父が旅立ったのは私がそばにいたときで、それは父が私なら耐えられると知っていたからなの。この役を演じることで、私は悲しみを乗り越えることができたし、その悲しみを役作りに生かせた。演技というものはとても大きな癒しにもなるのよ」
ベンジャミンは大人になるにつれ、死と平静に向き合えるようになる。それはほとんどの人間にはできないことだ。「彼が育った世界では、人々は自分の死というものを受け入れていた。だから、彼は死に対してはそんなに恐れなくなっていく」とフィンチャーは言う。「あの老人ホームで彼が出会うのは、一時的にしか彼のそばにいない人ばかりで、どの瞬間も、その人との最後の瞬間になり得る。だが、その人たちは決してヒステリックにはならない。誰もが自分の状況を受け入れているんだ。だから、まだとても幼いうちから、ベンジャミンは死というもののもっとも奥深い側面に慣れ親しんでいく。死は誰にもいつかは訪れるものだ。でも、多くの人は、その必然からなんとか逃れる道はないかともがきながら日々を送っている」
ベンジャミンとデイジーが初めて出会うのは、ふたりがまだ子供のとき。デイジーの祖母がノーラン・ハウスの入居者で、彼女が面会に来たときだった。彼女は、彼の衰えた体の奥にある子供らしさに気づく。「このストーリーの要のひとつは、ふたりの人生がどのように交わり、どのように離れていくかという点だ」とロスは言う。「彼らはさまざまなチャンスをつかんだり、逃したりしながら成長し、変わっていき、それに従ってふたりの関係も変化していく」
周囲の誰もが年をとっていく中、ベンジャミンはただひとり、若返っていく。「若返っていくたびにベンジャミンは、自分が誰かを、そして何かを、ずっと手元に置いておくことはできないと痛感する」と共演のマハーシャラルハズバズ・アリは言う。「彼は、自分のそばにそういうものがあるのは限られた時間だけであり、それを手放すことに慣れなければならないと分かっているんだ。そばにいるときには思う存分楽しむことができるが、それは決して永遠には続かない」
ベンジャミンがもつその“受容性”は、フィンチャーが自分の父に見いだしたものと同じだ。「僕はベンジャミンと父を重ねることが多い」と彼は言う。「僕の父はジャーナリストで、大恐慌時代に生まれた人なので、ちょっとストイックで、観察者的なところがあった。父は何事も決めつけなかった。ありのままの相手をいつも気持ちよく受け入れていたんだ。僕はそういうところを、ベンジャミンの態度、とくに、ほかの人や状況への対処の仕方に盛り込んだ。彼を見ながら、『そう、僕の父ならそうした。父はそんなふうに行動した』とね」
ベンジャミンをクイニーとともに育てたのは、それまでのさまざまな経験や人生から得た教訓を思い出にし、晩年を静かに過ごすためにノーラン・ハウスへやってきた年老いた人々だった。
クイニーの長年の恋人ティジーはベンジャミンにとって最初の父親的存在である。「ベンジャミンにとって、ティジーは大人の男のバロメーターみたいな存在なんだ」と、ティジーを演じるアリは言う。「ティジーはベンジャミンを導き、育てる。彼に読み書きを教え、シェイクスピアについても教える。だが、彼がベンジャミンに与えたもっとも大きな影響は、男とはこうあるべきという感覚だと思う。ティジーが彼にその基盤を与えたから、彼の人生に大人の男性の存在があるという点で、ベンジャミンは気持ちが落ち着く部分があると思うよ」
だが、ベンジャミンが出会い、愛するようになる人たちは皆、短い期間しか彼のものではない。ティジーも同じだ。やがてベンジャミンは、彼が唯一“わが家”と呼べる場所にクイニー、ティジー、デイジー、そしてほかの友たちを残し、世界へ旅立つ。彼を冒険に招いたのは、マイク船長と彼のタグボートの個性豊かな乗組員たちだ。
 ジャレッド・ハリス
ジャレッド・ハリス演じる、このゴマシオ頭の船長は全身に刻んだ刺青を通して隠された自分を明らかにしていく。ハリスはマイク船長をこう表現する。「彼は挫折感、欲求不満を抱き、酔っ払いで、うっぷんを抱えた芸術家のなりそこない、みたいな感じ。彼は父親に抵抗できずに、家業を継いだ」
自分も父親との確執があったにもかかわらず、マイク船長はベンジャミンにとってもうひとりの父親的存在となる。「父親というのは、人生で恐ろしく大きな影響力をもつ存在だよね」とハリスは言う。「そして、このストーリーの中では、男性キャラクター、そして父と息子の関係は、非常に大きな根本となるものなんだ。マイク船長は、ある意味、悪い父親とかおじさんみたいな感じで、人生の不道徳や喜びをベンジャミンに教える。彼はまた、ベンジャミンに海での生活を見せ、それによってベンジャミンは世界を見て回ることができるんだ」
だが、マイク船長もティジーと同様に、あくまでも父親“代わり”だ。ほんとうの父トーマス・バトンは、ベンジャミンをノーラン・ハウスの階段に置き去りにした。「トーマスは、怒りと将来に対する不安をすべて息子のせいにする」と言うのは、トーマスを演じるジェイソン・フレミング。「奇妙なことだが、妻を出産で失ったあと、彼は息子を捨てることにより、心の痛みから解放されると思い込んだんだ。だが、実際は、彼は残りの人生を悔やみながら過ごすことになる。その後悔の念に彼は永遠にとり憑かれるんだ」
ピットとフィンチャーの友人でもあるフレミングは、ロスの脚本に心酔したため、読んだあとで自らテープにセリフを吹き込んで売り込み、トーマス役を射止めた。「僕がこの役をどう演じられるかを、デビッドとシーアンにぜひ知ってほしかったんだ」と彼は思い返す。「これは僕が映画館で観たいと思うような映画になると分かっていた。その映画にどうしても参加したかったんだよ」
成人に達し、遠いロシアの港町ムルマンスクに来たベンジャミンは、そこで彼の人生において重要な役割を果たすもうひとりの人物と出会う。ティルダ・スウィントンが演じるエリザベス・アボットである。「ティルダは出演作を重ねるごとに、万能選手であることを証明してきたわ」とケネディは言う。「彼女がブラッド、ケイト、タラジ、そしてほかのすばらしい俳優たちと一緒にスクリーンに登場すると思うだけで、映画全体の輝きが増す感じだった」
英仏海峡を泳いで渡ることを夢見ている孤独なエリザベスは外交官の妻で、ベンジャミンのファースト・キスの相手となる。「ふたりはお互いから何かを学ぶの」とスウィントンは言う。「彼女はオープンで、エネルギッシュで、自分探しをしている。彼は辛抱強く、シンプルで、楽観的。ちょうどお互いを補える関係ね。彼女が人生の終盤に起こすある行動は、ベンジャミンに影響されたものなの。何かを始めようとすること、自分の足で生きていくこと、選択の意味、そして自分の人生は自分のためにあるべきだという主張……。私はそこに深い感動を覚えたわ」
ベンジャミンがタグボートで旅をしている間、デイジーも自分の人生を歩み、ニューヨークでバレエ団に加わる。若さの絶頂にいる彼女は、あふれんばかりの感情で大胆な行動に出たりする。「これは、『あなたなしでは生きていけない』というような、互いに依存し合う関係ではない」とフィンチャーは言う。「彼らは互いを待っているわけではないんだ。それぞれ、ちゃんと異性との関係はもっているしね。彼らはそれぞれの人生を歩んでいる完全に独立した個人であり、それが楽な道のりではないと知りながらも、ある一定の時間を共に過ごすことを選ぶ」
ふたりの道は分かれてはまた交わり、それはフィンチャーが「甘美な瞬間」と呼ぶときまで続く。そして、ようやく、ふたりは結ばれるべくして結ばれる。「彼らはまさにそうあるべき瞬間に、あるがままの自分になるように宇宙に仕組まれたんだ」とフィンチャーは言う。「ふたりが結ばれるとき、観客はきっとホッとすると思うよ。このタイミングならいい。そうなって当然なわけだからね」
ベンジャミンの世界に住むデイジーやほかの人々は、ストーリーが展開する中でそれぞれの人生の起伏を経験する。中心的なストーリーと関連して、あるいは表に出ない部分で、彼らの物語はこの映画のタペストリーに欠かせない糸なのだ。
「デビッドには自分自身の手で実際の素材を扱っていく芸術家的なセンスがあると思う」とスウィントンは言う。「彼にはアイデアが詰まってる。彼はハリウッド映画の伝統と、その限りない可能性の両方を、ほんとうのパイオニア精神でとらえているの。彼は砂場の子供と同じよ。彼は自分の頭の中で完全に映画を創り上げ、そこから単純にダウンロードしたものをスタッフと一緒に実際に創っていくような感じがするわ。彼は、まるで夢を思い出しているかのように、凝ったゲームの中で、自分の好きなものをつなぎ合わせていっているような……。彼のやることは、いつも驚きに満ちているの」
ピットも同感だ。「デビッドはまるで何かにとり憑かれたような男。彼には映像に対するすばらしい目があり、カメラワークのバランスは、彼にとってはもうそれしかないというものなんだが、それがまた最高なんだ。その結果、これだけ見事に練り上げられた作品が完成する。彼は彫刻家なんだよ」
「彼はひとつのアイデア、瞬間、イメージ、キャラクター、あるいはシーンを、あらゆる角度から熟考するの。ほかの人なら、ひとつのアイデアを3つの異なる次元で検討して満足するところを、デビッドは6つか7つの次元まで考えないと気が済まない」とブランシェットは付け加える。「誰かが、『デビッド、もういいだろ、とても無理だよ』なんて言うと、彼はいっそう燃えるのよ。この映画にしても、ほかの監督だったら、デビッドが到達できたところまで行く前に満足してやめてしまっていたと思うわ」
本作の撮影は、モントリオール、カリブ海、そして主人公の故郷ニューオーリンズなど、さまざまなロケーションでおこなわれた。撮影が始まったとき、ニューオーリンズはハリケーン・カトリーナの被害から復旧し始めていたときだった。「ニューオーリンズでの撮影を決めたのは、ハリケーン・カトリーナが襲来する前だったので、当然、あんな災害のあとで、撮影ができるかどうか不安も覚えたわ」とケネディは思い返す。「でも、ハリケーンの2日後に市から電話があり、計画どおり、ぜひ撮影してほしいと言ってきたの」
物理的、精神的に大きなダメージを被った直後の町での撮影には、物資調達などの面での難しさも伴った。「市からそれは大きな支援を受け、キャスト、スタッフがさまざまな場面で機転を利かせてくれたおかげで、それは小さな問題でしかなかった」とマーシャルは言う。「毎日の撮影を慎重に計画し、リハーサルを重ねたし、デビッドがあらゆる分野でリーダーシップを発揮して、誰もが状況を明確につかむことができた。だから、全体的に撮影はとてもスムーズに進んだよ」
フィルムメーカーたちは、困難な状況でも町の人々が気力を失っていないことにすぐに気づいた。「デビッドと私は、参加したいからそこにいる人たちと仕事ができて、とても恵まれていると思っているわ」とチャフィンは言う。「この映画の撮影に関して、とくにルイジアナでは、『あなたたちをぜひ迎えたい』と言ってくれる人たちがものすごくたくさんいたの。脚本を読んだ誰もが、そのどこかの部分に心を動かされ、それは人によってまったく違う部分なの。読んだ人たちは、自分自身の人生の何かと通じるものを感じ、この映画に参加したいと思ったんじゃないかしら」
ニューオーリンズの時代を超えた雰囲気は、この映画のさまざまな時代にピッタリとはまった。「映画の中では、あからさまに時間の経過を示さずに、それぞれの時代をはっきり描くことがとても重要だったんだ」と美術監督のドナルド・グレイアム・バートは言う。「同じセットの中で自然な時間の経過の雰囲気を創り出すことはもっと大事だった。セット・デコレーターのビクター・J・ゾルフォと話し合い、セットのどの要素を変えるべきか、どれをそのまま残すべきかを決めていったんだ。どの要素もちゃんと理由があってそこに置かれることが大事だったんだ。隙間があるから埋めるとか、変化をつけるというだけのためじゃなくてね」
フィンチャーがそれぞれのセットに生み出したいと思ったのは、誰かの家の屋根裏部屋から持ち出した、ごく普通の人生を送っている素朴な一家の写真で埋まっているアルバムをめくっていくような雰囲気だ。「僕たちは、ベンジャミンの人生で大事な出来事が起こる場所、とくにノーラン・ハウスと、ベンジャミンがエリザベスと出会うムルマンスクのホテルについては、それぞれ架空の歴史を考え出した」とゾルフォは言う。
撮影のどの段階においても、ストーリーの核にある本質的な真実を育むような、説得力のあるリアリズムを創り出すことが絶対的な課題だった。「このストーリーには、寓話的な要素がたくさんあるとはいえ、リスクを冒してでも、できるだけリアルに描きたいと思った」とフィンチャーは説明する。「僕はこの映画を『昔あるところに……』のような昔話の世界にはしたくなかった。俳優たちに思い込みで演技をさせたくなかった。観客に勝手に想像させたくなかった。美術監督に突拍子もないセットを作らせたくなかった。場所の様子、人々の服装、彼らのメガネや補聴器など、すべてが時代に合っていなければならなかったんだ」
衣装もまた、その当時に合わせたものだが、様式化された。衣装デザイナーのジャクリーン・ウエストは、美術と衣装の調和がとれるように、早い段階でバート、ゾルフォと打ち合わせをした。「デビッドは画家のようにひとつのシーンを構成するの」とウエストは言う。「鉄道のセットに行ったときは、ギュスターヴ・カイユボットの絵画のようだと思ったので、参考にするために、カイユボットやほかの初期印象派の作品――エドゥアール・マネ、トゥールーズ=ロートレック、ギュスターヴ・クールベなど――を見に行ったの。美術のドナルドのすばらしい感覚をしっかりつかめさえすれば、暗褐色やくすんだ色の多い私の色づかいの範囲でそこにどんな衣装をもってこようとうまく調和させられる自信があった」
ウエストはベンジャミンの“若い”時代に登場するクイニーの衣装のヒントを得るため、大恐慌時代に設立されたWPA(雇用対策局)とFSA(農業安定局)の写真を調べた。「クイニーは貧しいけれど、とても個性豊かな女性なので、私はその人柄を衣装に反映したかったの。それに、彼女の服はノーラン・ハウスで最後の時を過ごした老婦人たちが遺したものがほとんどだったと思う。彼女たちはたぶん、亡くなる20年ぐらい前から買い物はしていなかったはず。だから、ちょっと時代遅れの雰囲気も出したの」
それとは対照的に、デイジーにはつねに当時の最新ファッションと体にピッタリ合ったバレエ用レオタードを身に着けさせた。ウエストがデイジーのために参考にしたのは、進歩的なバレエ振付師ジョージ・バランシンと、彼の妻でミューズだったタナキル・ルクラークで、彼らからはブランシェット自身もインスピレーションを受けていた。「私はデイジーの若い時代に影響力のあったダンスを参考にしたの」とブランシェットは説明する。「その中でも、バランシンとルクラークにはとくに興味をもったわ」
衣装を身に着けたケイトはバレリーナそのものになったとウエストは言う。「彼女を見ながら私はルクラークの写真から受けた印象を思い出していたの。ボディ・ランゲージ、身のこなし、心の葛藤……そんなものすべてを」
ルクラークが気に入っていたのは、40年代、50年代のアメリカでトップ・デザイナーだったクレア・マッカーデルで、“アメリカン・ルック”と呼ばれる既製服の流れを作った人物として知られる。
本作の中でデイジーのもっとも印象的な衣装のひとつ――ベンジャミンとのデートで着た優美な赤いドレス――を、ウエストはマッカーデルのデザインをヒントにして考えた。ブランシェットはこう言う。「ジャクリーンと私の好みはピッタリ一致していたの。私はあのドレスのどの縫い目もどのボタンも愛おしかったわ。彼女のおかげでクレア・マッカーデルを知ったんだけど、あの衣装合わせで私は新しい発見をした気がする。今回、私はほんとに恵まれていたと思う」
ベンジャミンの衣装を生涯を通して考えるうえで、ウエストは20世紀を代表する映画スター数人にヒントを求めた。「私が参考にしたのは、40年代のゲイリー・クーパー、50年代のマーロン・ブランド、そして60年代のスティーブ・マックイーン。彼らは皆、大きな影響力をもっていたし、ブラッドには同じようなカリスマ性があるので、彼ならきっと、あの雰囲気をモノにできると思ったの」と彼女は言う。
さて、ベンジャミンを老人に見える時代から若く見える時代まで演じることとなったピットは、衣装だけでなく、デジタル技術の助けも借りて役になりきった。フィンチャーとは長年組んでいる視覚効果監修のエリック・バーバはこう語る。「デビッドからは最初に言われたんだ。『ブラッドは最初から最後までベンジャミンを演じるからな』って。この映画の感情面を動かすのはベンジャミンであり、どんなシーンでも明確な存在感がある。そこにいないはずでもね。そこが視覚効果チームとしてはやりがいのあるところだった」
バーバと二人三脚でブラッドの変身に取り組んだのは、これまでにアカデミー賞にも輝いている特殊メイクアップ・デザイナーのグレッグ・キャノム。彼は全編を通じて、ベンジャミンの老けメイク、そして若返りメイクを効果的に見せるためのプロテーゼ(人工装具)を作った。
広大なカンバスの上で、地味だが、細部までこだわるフィンチャーの方針は、本作で使用されたデジタル撮影にまで浸透した。「この映画におけるデビッドの撮影スタイルは、デビッド・リーンがかつて、場所と時代の感覚をとらえる大胆で大がかりな映像で実証してみせた撮影スタイルに挑むものでもある」とマーシャルは言う。「デビッド・フィンチャーは観察者としてカメラを活用することによって、このストーリーの痛切な心情を最大限に生かしている。彼は観客を巻き込んで性格描写をしたいので、カメラワークはより検討され、静かになる。これは素早いカットや、本能に任せためまぐるしいカメラワークは必要とされない映画なんだ」
撮影監督のクラウディオ・ミランダは、「できるだけ自然な照明にしたかった」と言う。「僕たちは光源がどこから来るかを見極め、それを工夫しようとしたんだ。フレーム内に電球を置いて、そのシーンを照らしただけの映像もあったよ。通常は、電球を置くことで光源がそこだと思わせ、明るさをしぼって強くならないようにし、実際はフレームのすぐ外に別の光源を置くものなんだけどね。あのシーンでは、自然なままの照明で撮影できてすごくよかった」
ストーリー上の時代の推移に従って光源も変化し、あるものは別のものにとって代わられた。「ろうそく、ガス・ランプ、透明電球、白熱電球、蛍光灯……と時代とともに技術は進歩していく」とフィンチャーは説明する。「映画用の照明も使ったが、そんなに多くはない。ほとんどの部分は、それらの光源を利用できるように、また、素早く進められるようにデジタル撮影をした」
その場の環境をそのまま利用した映像もある。ニューヨークに帰る前の晩、デイジーがベンジャミンとデートをし、あずま屋風の場所でデイジーが踊る優雅なシーンがそのひとつだ。「あのシーンはとてもシンプルだった。あのあずま屋を見たとき、絶対にあそこで撮らなきゃと思ったんだ」とフィンチャーは思い返す。「背景をどうしようかということが懸案事項になったが、僕は、『あそこに沼がある。蒸気か煙を漂わせ、木々をライトアップして、彼女をシルエットで写そう』と言った。僕らは昔ながらのハリウッド・スタイル、極めてシンプルなシーンにしようとした。あれはまるでオルゴールのように見えたよ」
フィンチャーの鋭い感覚と、細部に対するこだわりは、ベンジャミンの生涯の中心にある真実を彼がいかに深く理解しているかを示すものでもあった。「このストーリーの壮大さと、深い感情の動きを考えると、デビッドの選択はどれをとっても完璧だった。おかげで、この作品に参加した私たち全員がとても報われた気持ちになれたわ」とケネディが締めくくる。

cast
ベンジャミン・バトン・・・・・・・・・・・・・ブラッド・ピット
デイジー・・・・・・・・・・・・・ケイト・ブランシェット
クイニー・・・・・・・・・・・・・タラジ・P・ヘンソン
キャロライン・・・・・・・・・・・・・ジュリア・オーモンド
トーマス・バトン・・・・・・・・・・・・・ジェイソン・フレミング
ムッシュ・ガトー・・・・・・・・・・・・・イライアス・コーティーズ
エリザベス・アボット・・・・・・・・・・・・・ティルダ・スウィントン
マイク船長・・・・・・・・・・・・・ジャレッド・ハリス
デイジー(幼少期)・・・・・・・・・・・・・エル・ファニング
ティジー・・・・・・・・・・・・・マハーシャラルハズバズ・アリ
Staff
監督:デビッド・フィンチャー
脚本/映画版原案:エリック・ロス
映画版原案:ロビン・スウィコード
原作:F・スコット・フィッツジェラルド
製作:キャスリーン・ケネディ,フランク・マーシャル,シーアン・チャフィン
撮影: クラウディオ・ミランダ
美術:ドナルド・グレイアム・バート
編集:カーク・バクスター,アンガス・ウォール
衣装:ジャクリーン・ウエスト | 音楽:アレクサンドル・デプラ
視覚効果監修:エリック・バーバ | 特殊メイク効果:グレッグ・キャノム
2008年アメリカ映画|2009年日本公開作品|原題:THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON
時間:167分/10巻/4,590m/シネマスコープサイズ/SRD・DTS・SDDS
翻訳(字幕・吹替):アンゼたかし|吹替版演出:小山悟
原作:F・スコット・フィッツジェラルド
配給:ワーナー・ブラザース映画
オリジナル・サウンドトラック:ユニバーサル クラシックス&ジャズ
(c)2008 Paramount Pictures Corporation and Warner Bros. Entertainment All Rights Reserved.
http://wwws.warnerbros.co.jp/benjaminbutton/
2009年2月7日(土)より、丸の内ピカデリー他全国ロードショー
 ゾディアック ディレクターズカット
ゾディアック ディレクターズカット(Blu-ray Disc)
監督:デビッド・フィンチャー
出演:マーク・ラファロ,ロバート・ダウニーJr.,ジェイク・ギレンホール
ワーナー・ホーム・ビデオ
発売日: 2008-07-09
おすすめ度:
Amazon で詳細を見る
主なキャスト / スタッフ
TRACKBACK URL:

