グラン・トリノ
2009年4月25日(土)より、丸の内ピカデリー他にて全国ロードショー

男は迷っていた、人生の締めくくり方を――。
少年は知らなかった、人生の始め方を――。
そして、二人は出会った。
 監督を兼ねる本作で、オスカー受賞作『ミリオンダラー・ベイビー
監督を兼ねる本作で、オスカー受賞作『ミリオンダラー・ベイビー』(04)以来の映画出演をはたしたクリント・イーストウッド。今回の役どころは朝鮮戦争の帰還兵ウォルト・コワルスキーだ。偏屈で頑固なコワルスキーが隣人との交流を通じて、自らの先入観や偏見を改めていく。
ウォルト・コワルスキーの日常は、自動車工の仕事をリタイアして以来、同じことの繰り返しだ。自宅を修繕し、ビールを飲んで一日が過ぎ、月に一度床屋に行く。亡き妻は最期の願いとしてウォルトに懺悔(ざんげ)を勧めた――今までの罪を告白し、神の許しを乞うてほしいと。しかし、ウォルトにしてみれば懺悔することなど何もない。かつて朝鮮戦争に出兵したウォルトは今もM1ライフルを手元に置き、ピカピカに磨きあげている。罪を告白するほど心を許せる相手がいるとしたら、それは愛犬のデイジーくらいだ。
そんな彼が「隣人」と呼んでいた顔なじみは引っ越したり、亡くなったりして、誰ひとりいなくなってしまった。今では近所に東南アジアからやって来たモン族が住み着いているが、ウォルトにはこれが気に入らない。というより、この近所で目にするものすべてがいまいましかった。どの家も軒は崩れかけ、庭の草木は伸び放題。住民は外国人だらけだ。モン族、ラテン系、アフリカ系の若いゴロツキはグループを作って、我が物顔で通りを歩く。ウォルトにも成人した息子たちがいるが、他人も同然だ。今のウォルトは、ただ死ぬのを待っているかのようだった。
ある晩、何者かが自慢のグラン・トリノを盗みに入るまでは――。
その72年製のフォード車は、ウォルト自身が自動車工として手がけた一台で、今も新車同様の輝きを放っている。このグラン・トリノが縁となり、ウォルトはタオ(ビー・バン)というシャイな少年と知り合うことになる。タオはモン族の不良グループにけしかけられて、ウォルトのグラン・トリノを盗もうとしたのだ。
それをウォルトが未然に防ぎ、計らずも町内の英雄に祭り上げられる。とりわけタオの母親と姉スー(アーニー・ハー)はウォルトに感謝することしきり。おわびのしるしとして、タオに奉公させたいと言い出すしまつだ。最初は移民の一家と関わりたくないと思っていたウォルトだったが、ついに根負けし、タオに家の修繕を手伝ってもらうことにする。やがて、ふたりの間に思いがけない友情が芽生え、それぞれの人生を大きく変えていく。
ウォルトはタオ一家の誠意に触れるうち、彼らの現実を、そして、自分自身の本心を知る。痛ましい過去をもつモン族の隣人は、ウォルトにとって本当の家族以上に通じ合える存在だった。そんな隣人との交流がウォルトの心を開いていく。あの戦争以来、固く閉ざされていた心の扉――それは暗いガレージにしまい込まれたグラン・トリノそのものだった。
2009年4月25日(土)より、丸の内ピカデリー他にて全国ロードショー

 ウォルト・コワルスキー(クリント・イーストウッド)には、自分だけの正義があった。それに外れるものは、何もかも許せない頑固で偏狭な男だ。
妻の葬儀では、孫娘の露出過剰なファッションにキレ、大勢の参列者は「会食に出すハムを食いに来ただけだ」と一刀両断。説教が気に入らない新米神父には、「頭でっかちの童貞」と毒づく。ふたりの息子たちは、式が済むと逃げるように帰って行った。
もっと、許せないことがある。近隣に暮らす、ウォルトが偏見を隠さないアジア系の移民たちだ。大人たちは家屋の手入れをせず、若者たちはギャングを気取って異人種間の小競り合いを繰り返している。
ウォルト・コワルスキー(クリント・イーストウッド)には、自分だけの正義があった。それに外れるものは、何もかも許せない頑固で偏狭な男だ。
妻の葬儀では、孫娘の露出過剰なファッションにキレ、大勢の参列者は「会食に出すハムを食いに来ただけだ」と一刀両断。説教が気に入らない新米神父には、「頭でっかちの童貞」と毒づく。ふたりの息子たちは、式が済むと逃げるように帰って行った。
もっと、許せないことがある。近隣に暮らす、ウォルトが偏見を隠さないアジア系の移民たちだ。大人たちは家屋の手入れをせず、若者たちはギャングを気取って異人種間の小競り合いを繰り返している。
彼らに罵声を浴びせる以外のウォルトの日常は、いたって退屈だ。自宅を修繕し、芝生を刈り、愛犬デイジーに語りかけながらビールを飲み、月に一度は床屋へ行く。そんな彼の唯一の楽しみは、磨き上げた愛車〈グラン・トリノ〉を眺めること。定年までフォードの自動車工を勤め上げたウォルトが、1972年に自らステアリング・コラムを取り付けたヴィンテージ・カーだ。
その宝物を盗もうとする、命知らずの少年が現われる。隣に住むモン族のタオだ。学校にも行かず仕事もないタオは、従兄のスパイダーに不良グループへ引き込まれ、車を盗めと命令される。夜中にガレージに忍び込んだタオは、ウォルトにM-1ライフルを向けられて、逃げ出した。ウォルトは、朝鮮戦争で使い込んだそのライフルを、タオにヤキを入れに来たスパイダーたちにも突きつける。彼は自宅の庭に侵入されて激怒しただけなのだが、タオを不良たちから救う結果になるのだった。
翌日、タオの母と姉のスー、そして親戚までが、花に植木、料理にお菓子とお礼を持って押しかけるが、ウォルトには迷惑なだけだった。数日後、ウォルトはスーが黒人の二人組に絡まれているところを助けてやる。朗らかで機転の利くスーとの会話は、ウォルト自身意外なことに実に楽しいものだった。
また別の日、ウォルトはスーから自宅に招待される。ビールに釣られて訪ねると、最初は気まずい空気が流れるが、祈祷師に心の中をズバリ言い当てられ、女たちに美味しい料理を振る舞われ、ウォルトは思わず「どうにもならない身内より、ここの連中のほうが身近に思える」と呟く。
今度はスーと母親がウォルトを訪ね、お詫びにタオを働かせてほしいと強引に頼みこむ。渋々引き受けたウォルトとタオの不思議な交流が始まった。近隣の家の修繕を命じられたタオは、労働の喜びに目覚めていく。手本となる父親がいないタオにとって、ウォルトはまさに人生の師だ。ウォルトもまた、生き生きと働くタオを見直し始める。約束の日数が過ぎても、タオは何かとウォルトを手伝った。
タオに建設現場の仕事を世話し、自慢の工具を貸し与えるウォルト。今やウォルトは、タオを一人前の男にするという人生の最後に相応しい仕事に、生きる喜びを感じていた。何もかもが順調に見えた時、スパイダーたちの嫌がらせが再燃する。ウォルトが受けて立ったばかりに争いはさらに加速し、ウォルトはタオと家族の命の危険さえ感じ始める。タオとスーの未来を守るため、ウォルトがつけた決着とは……?
2009年4月25日(土)より、丸の内ピカデリー他にて全国ロードショー
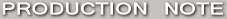
時代は変わった
 ベテランの俳優、監督として映画史に残る名作を放ってきたクリント・イーストウッドだが、カメラの前に立つのはオスカーに輝いた『ミリオンダラー・ベイビー
ベテランの俳優、監督として映画史に残る名作を放ってきたクリント・イーストウッドだが、カメラの前に立つのはオスカーに輝いた『ミリオンダラー・ベイビー』(04)以来だ。「実を言うと、俳優業は控えようと考えていたんだ」とイーストウッドは明かす。「ところが、この作品には同年代のキャラクターが出てくるし、そのキャラクターというのが僕のことを念頭に置いて書かれたんじゃないかと思うような男だった……本当は違うんだけどね。それに、脚本もすばらしかったよ。ひねりが効いていて、ところどころに笑いを含んでいたからね」
イーストウッドの制作会社マルパソに届いたその脚本は、新人のニック・シェンクが執筆したもの。本作で映画脚本家としてデビューしたシェンクはパートナーのデイブ・ジョハンソンとともに原案も練り上げた。「今回のストーリーはニックとデイブの実体験がもとになっている。故郷のミネソタで見聞きしたことや地元の人々との交流が下敷きなんだよ」とプロデューサーのロバート・ローレンツは言う。ローレンツは、イーストウッドが全幅の信頼をおく旧知のパートナーだ。「この脚本は製作総指揮のジェネット・カーン、製作のビル・ガーバーを経由して我々の手元に届いた。僕も最初はハイペースで読んでいた。クリントが出演するとは想像すらしていなかったからね。でも、途中からペースを落として、じっくり読むようになった。とてもよくできた脚本だったんだ。もう一度読み直してみたが、やはりすばらしい。クリントにゴリ押しは無用だが、とりあえず脚本を手渡して言ったんだ。『これが君の監督作になるか出演作になるかはわからないけれど、とにかくおもしろいよ』と。後日、クリントから電話で『あの脚本、とてもいいね』と返事があった。そこから、すべてが始まったんだ。」
シェンクによれば、ウォルト・コワルスキーというキャラクターは特定の俳優をイメージして創作したものではないそうだ。「ウォルトは手先の器用なおじさん、あるいは、ガミガミ親父という感じ。人が自転車を組み立てていれば、横からあれこれ口を出してくるようなタイプなんだ。そういうおじさんは町内に一人はいるんじゃないかな」
ミネソタ州出身のシェンクは地元の工場で働いていたことがある。当時の仕事仲間には、モン族の移民が大勢混じっていた。モン族はラオスをはじめとするアジア各地に散在し、ベトナム戦争時には米軍を支援したが、その文化はほとんど知られていない。「たしかにモン族の文化は見えにくい」とシェンクもうなづく。
ウォルトは一見すると筋金入りの人種差別主義者だ。普段の会話でも差別語を連発するのだが、そんな彼も近隣に越してきたモン族の一家と触れ合ううちに、とげとげしい言動はなりをひそめていく。「ウォルトは朝鮮戦争で体験した悪夢に、今も苦しめられていて、隣人を見ると当時を思い出してしまうんだ」とシェンク。「彼にとってアジア人はみんな一緒。同じに見える。そんなウォルトの前に実態のわからない民族が現われた。彼らのことを知るにつれ、自分はあの戦争で何をしたのか考えるようになるんだ」
製作のビル・ガーバーが指摘するように、本作は人間関係の機微を描いている点で過去のイーストウッド作品に通じるものがある。「クリントは昔から人種、宗教、社会的偏見といった重いテーマを正面から取りあげてきた。それを不適切と見る向きもあるかもしれないが、社会の現実であることは間違いない」とガーバー。「イーストウッド作品のファンなら察しがつくと思うが、今回の主人公であるウォルトも見た目どおりのキャラクターではない。その素顔は最初は見えないけれど、隣人との関係が深まるにつれて、だんだんと見えてくるんだ」
「この作品の監督も、ウォルトを演じる俳優も、クリント・イーストウッド以外は考えられない」と原案を担当したデイブ・ジョハンソンが断言する。「監督としてのイーストウッドは本当に器が大きくて、どんなにきわどいテーマにも物おじしない。俳優としても、ウォルトを演じるには相当な度胸が必要だったと思う。ウォルトは、お世辞にもかわいげがあるとは言えないキャラクターだから。ウォルトは60年間ずっと偏屈な男で通してきた。それほど染みついたものを変えるのは、かなりの勇気がいるはず。特に晩年になったらなおさら至難の業だ。ウォルトは見た目もたくましいけれど、ストーリーが進むに従って、内面のたくましさも現わしていくんだ」
 本作のストーリーは、妻のドロシーを亡くしたウォルトが人生の最終章にさしかかったところからスタートする。それ以前のウォルトは悪夢のような朝鮮戦争を体験し、フォードの自動車工場に半世紀ほど勤務した。しかし、今となっては戦争も遠い昔、自動車工場も閉鎖され、妻はこの世にいない。ふたりの息子はそれぞれ独立して、めったに顔を見せない。「ウォルトは懸命に働いてきたし、息子たちもそれなりに出世している」とイーストウッドが説明する。「けれども妻に先立たれ、息子たちとも疎遠になってしまった。息子たちは父親に近づこうせず、愛想を尽かしているんだ。ただ、息子の立場から言えば、ウォルトは決してとっつきやすい父親じゃない。超のつくへそ曲がりだし、孫のピアスにも文句を言うくらいだからね」
本作のストーリーは、妻のドロシーを亡くしたウォルトが人生の最終章にさしかかったところからスタートする。それ以前のウォルトは悪夢のような朝鮮戦争を体験し、フォードの自動車工場に半世紀ほど勤務した。しかし、今となっては戦争も遠い昔、自動車工場も閉鎖され、妻はこの世にいない。ふたりの息子はそれぞれ独立して、めったに顔を見せない。「ウォルトは懸命に働いてきたし、息子たちもそれなりに出世している」とイーストウッドが説明する。「けれども妻に先立たれ、息子たちとも疎遠になってしまった。息子たちは父親に近づこうせず、愛想を尽かしているんだ。ただ、息子の立場から言えば、ウォルトは決してとっつきやすい父親じゃない。超のつくへそ曲がりだし、孫のピアスにも文句を言うくらいだからね」
ウォルトの息子ミッチ・コワルスキーに扮するブライアン・ヘイリーも同じ意見だ。「ウォルトみたいな親父はやっかいだよね。ミッチとウォルトは水と油。ウォルトは地道に働くブルーカラーだけど、ミッチは派手なヤング・エグゼクティブさ。ふたりの親子関係は微妙だよ。ウォルトは息子に何を話せばいいかわからないし、ミッチは父親とどう接していいかわからないんだ」
そして、ウォルトを放っておいてくれないのが、ウォルトの亡き妻が信頼を寄せていたヤノビッチ神父。ヤノビッチは彼女の遺志をかなえるべく、ウォルトに食い下がる。「クリント・イーストウッドに門前払いを食らうのが僕の役どころ」とヤノビッチに扮するクリストファー・カーレイは笑う。「ヤノビッチはやみくもにウォルトに理解を得ようとするんだ。せめて話だけでも聞いてほしいと。けれども、ウォルトは相手が神父だからといって敬意を払うこともない。ヤノビッチのことは“27歳のインテリ童貞”くらいにしか思っていないからね(笑)。ウォルトはこう言い放つんだ。『世間に通用するやり方は俺には通用しない』と」
イーストウッドがコメントする。「ウォルトはヤノビッチ神父を色眼鏡で見ているふしがある。神父は粘り強く贖罪を勧めるんだが、ウォルトにとって彼は“神学校を出たばかりの教科書どおりの優等生”でしかない。だから、ふたりの関係はいつも一方通行。ウォルトに『バテレン』呼ばわりされるヤノビッチだが、なかなか気骨がある。でも、ウォルトのほうが一枚上手なんだ」
ウォルトの唯一の楽しみはグラン・トリノの手入れだ。この72年製の愛車にシルクのシートをかけ、自宅のガレージに大切にしまいこんできた。フォードの自動車工場で、この車にハンドルを取りつけたのはほかならぬウォルトである。「あのグラン・トリノは自慢の息子なんだ」とイーストウッド。「というより、ウォルト自身だね。運転するわけでもなく、ただガレージに置いているんだが、ときどき外に出してワックスをかけてやる。ビール片手に愛車を眺めるのが老後のいちばんの楽しみなんだ」
古びた二階家が軒を連ねる町内で、ウォルトの家はひときわ目を引く。外壁の塗装も草木の剪定も完璧。庭先には星条旗が高々と掲げられている。だからこそ、近隣の景観の悪化に耐えられない。「彼は慣れ親しんだ世界が消えてしまったことを非常に苦々しく思っている」とイーストウッド。「ウォルトが育ったミシガンは自動車産業で栄えた。洗練されたアメリカ人が大勢住んでいて、ウォルトもその一人だったんだ。だから、周囲の景色がさびれていくのを見るのが忍びない」
近隣の住宅が老朽化していくなか、ウォルトの家だけは手先の器用な家主のおかげでメンテナンスが行き届いている。「ウォルトは町内で浮いた存在」と製作のローレンツは指摘する。「ウォルトは今も過去にしがみついたまま。心の中につかえがあり、そのせいで前へ進めない。そんなもどかしさが彼の人生に大きな影を落としているんだ」
 もうひとり、町内で孤立しているのがタオという16歳の少年だ。タオは祖母、母、姉と一つ屋根の下で暮らしている。「一家の中で男はタオだけ。だから、男として手本になる人も先輩にあたる人もいない。タオが弱虫で自信がないのは女系家族の中で育ってきたからじゃないかな。タオは先生のような存在を求めていた。そして、ウォルトを師と仰ぐ」
もうひとり、町内で孤立しているのがタオという16歳の少年だ。タオは祖母、母、姉と一つ屋根の下で暮らしている。「一家の中で男はタオだけ。だから、男として手本になる人も先輩にあたる人もいない。タオが弱虫で自信がないのは女系家族の中で育ってきたからじゃないかな。タオは先生のような存在を求めていた。そして、ウォルトを師と仰ぐ」
おとなしいタオは高校にも行かず、仕事もせず、いつのまにかモン族の不良グループに引き込まれてしまう。グループのリーダー格はスモーキーという少年と、タオのいとこの通称スパイダーだ。「タオはどこへ行ってもいじめられてしまうんだ」とスモーキー役のソニー・ビューは指摘する。「タオはひとりでは何もできないけれど、仲間がいればかばってもらえる。こういうグループを作る目的は他のグループから身を守るためなんだけど、スモーキーたちはウォルトに脅されてから暴走を始めてしまう。もっとタフにならなければ、男らしくならなければと焦るんだ」
スモーキーもスパイダーもモン族のなかではアメリカに生まれた最初の世代。モン族の伝統を教えてくれる大人は周りにいない。上の世代はアメリカ文化になじむのに、もっと苦労しているからだ。スパイダーを演じるドゥーア・ムーアが説明する。「ふたつの文化を生きることにはかなりの抵抗を感じるもの。だから少年たちは徒党を組んで、自分の居場所を確保しようとする。その点、女の子は家族を頼りにする傾向があるし、母親を先生にできるから、自分の境遇や親に反発することも少ないんじゃないかな」
タオはグループの一員になった証として、ウォルトのグラン・トリノを盗み出すようにリーダーから命じられる。「タオは自分も男だということを証明したい、グループに認められたいと思うんだ」とビー・バンは言う。ところが、その試みは失敗に終わる。盗みに入ったタオの前に突然ウォルトが現われたのだ。タオは相手の顔も見ずに尻尾を巻いて逃げ出す。「あれはタオの惨敗だよ」とビー・バン。「そのせいで盗みに入る前より臆病者になってしまうんだ」
ほどなくしてグループのメンバーがタオのもとに駆けつけるが、そこで小競り合いが起き、少年たちはウォルトの家の庭先に足を踏み入れてしまう。ウォルトは戦場から持ち帰ったM-1ライフルをちらつかせながら、少年たちに警告する――うちの芝生に入るな!
「ウォルトは一気に戦闘モードに入ってしまうんだ。と同時にモン族のコミュニティが抱える深刻な問題にも気づく。特に、少年グループの問題にね」とイーストウッド。
このときの勇敢な行動が称えられ、ウォルトは期せずして町内のヒーローになった。さらにはモン族の隣人から食料、花、草木などのプレゼント攻めにあう。「ウォルトは彼らと関わりをもちたくないんだ」とイーストウッドは続ける。「けれども、モン族の人たちが知的で義理堅いことを知って、考えが変わる。ウォルトのセリフに『のぼせ上がったうちのせがれより、この人たちのほうによほど親しみを感じる』というのがあるんだけど、それがすべてを物語っていると思う。あれほど偏見に満ちていたウォルトがモン族の人々と接するなかで、頑固な偏見から解き放たれていく。その姿はおもしろくもあり、おかしくもあるよ」
ウォルトのとげとげしい態度を和らげられる唯一の人間が、タオの姉のスーだ。しっかり者のスーは一家の誰よりもアメリカナイズされている。「ウォルトは好き放題に悪態をつくの」とスー役のアーニー・ハーは指摘する。「相手がどこの出身だろうと、おかまいなし。思ったことは何でも口に出してしまうのよ」。そして、スーというキャラクターについては「本当にたくましい女の子だと思うわ。ウォルトに対して、いつも丁重に接する。ときどき『ウォーリー』なんて呼んでからかうことはあってもね。それに、ウォルトとタオを引き合わせたのもスーなの。ウォルトが弟と仲良くしてくれることを願っているんでしょうね。そうしないと、弟は悪い仲間に入って将来を棒に振ってしまうかもしれない。ウォルトならタオの父親代わりになってくれるとスーは期待しているの。タオもウォルトについていれば、きっといい将来がひらけるし、まっとうな人間になれるはず」
 ウォルトとスーはすんなり打ち溶ける。「スーはうわべだけでなく心の底からウォルトのことを気にかけていると思う。でも、ウォルトの身内は違う。ただ機械的に、義務として彼に接しているにすぎない」と製作のローレンツは分析する。「スーの誠意を感じるからこそ、ウォルトは彼女に心を開くんじゃないかな」
ウォルトとスーはすんなり打ち溶ける。「スーはうわべだけでなく心の底からウォルトのことを気にかけていると思う。でも、ウォルトの身内は違う。ただ機械的に、義務として彼に接しているにすぎない」と製作のローレンツは分析する。「スーの誠意を感じるからこそ、ウォルトは彼女に心を開くんじゃないかな」
スーは家族の祝いの席にウォルターを招くことに成功する。そこにはモン族のシャーマンも同席。そして、シャーマンのお告げを通じてウォルターが今まで語らずにいた真実が明かされる。ローレンスは言う。「この一家のおもしろいところは――これはシャーマンとのやりとりではっきりわかることだが、歯に衣着せずものを言うところ。実の息子でも言えないようなことをウォルトに向かってズバリ指摘する。彼らが痛いところをついたり、立ち入った質問をしたりするので、ウォルトは否応なしに我が身を振り返る。これほど反省を促されたことはなかったはずだが、そこがウォルトの悪いところ。今まで自分に都合の悪いことはいっさい考えないようにしてきた。だから偏見の塊になってしまったんだ。それまでのウォルトはトラブルが起きれば、怒りの矛先を外へ向け、人のせいにしていた。自分の心を見つめ、我が身を改めようとはしなかった。でも、モン族の隣人によって、そうせざるを得なくなるんだ」
ウォルトの愛車を盗みに入ったタオは母と姉に背中を押され、罪滅ぼしとしてウォルトの仕事をしばらく手伝うことにする。「ふたりは一家の威信をかけて、タオにつぐないをさせようとするんだ」とイーストウッドは言う。
手伝いにやってきたタオに対してウォルトは蔑称を連発。タオの名をわざと「トード(バカ、ヒキガエルの意)」と言い違えてみせる。それでもタオは役に立とうと懸命になり、ウォルトと一緒に近所のボロ家を修繕。ウォルトはタオを見直すのだ。「そこから、ふたりの間柄は変わっていく」とタオ役のビー・バンは言う。「ウォルトはタオの成長ぶりに感心するんだ。最初のころに比べれば、ずいぶん大人になったし、日に日にたくましくなるからね。タオも両手にタコを作って誇らしい気分になる。自分もようやく何かの役に立てた、役に立つ人間になれたんだと」
ウォルトの最終目標は“タオを一人前にすること”だ。ビー・バンが続ける。「ウォルトはただ仕事を教えているだけじゃない。タオに男としての自信をつけてやろうと考えているんだ。そうすれば悪い仲間とつるむ必要もなくなる。ウォルトはタオに人生のいしずえを与えてやるんだよ」
生きる当てのなかった少年に仕事をもたせ、まっとうな生き方を教え、将来の道筋をつけてやることはウォルトの生きがいになる。そしてタオとの奇妙な二人三脚はウォルト自身をも変えていく。製作のローレンツが語る。「タオには頼れる父親、手本になる父親がいない。そしてウォルトには親としての喜びを実感できるような親子関係がない。だからふたりのニーズは一致するんだ。ウォルトは探していたんだよ――晩年を迎えた今、人生の集大成となるような仕事を、そして、生きてきて良かったと思わせてくれる相手をね」
一方、スモーキー率いる不良グループはタオの一家に繰り返しいやがらせをし、脅迫まがいの行動に出る。そこで再び“老兵ウォルト”は立ち上がり、まったく経験のない任務を背負うことになる。「毒を食らわば皿まで、だよ」とイーストウッド。「ウォルトは中途半端を嫌う男。何をするにも徹底しているんだ」
見知らぬ隣人
 モン族がメジャーな映画で取りあげられるのは今回が初めて。モン族の18の氏族はラオス、ベトナム、タイなどアジア各地に散在しているが、とりわけラオスのモン族はベトナム戦争後にアメリカへ移住し、大変な苦労を強いられた。「彼らのことは詳しく知らなかった」とイーストウッド。「ベトナム戦争でアメリカ軍に加担し、戦争が終わるとともに避難民として受け入れられた。知っていたことと言えば、そのくらいかな」
モン族がメジャーな映画で取りあげられるのは今回が初めて。モン族の18の氏族はラオス、ベトナム、タイなどアジア各地に散在しているが、とりわけラオスのモン族はベトナム戦争後にアメリカへ移住し、大変な苦労を強いられた。「彼らのことは詳しく知らなかった」とイーストウッド。「ベトナム戦争でアメリカ軍に加担し、戦争が終わるとともに避難民として受け入れられた。知っていたことと言えば、そのくらいかな」
「私たちがあの戦争でどんな役割を担ったか。悲しいことに、それを知る人はほとんどいないんです」とモン族のスタッフのポーラ・ヨウは話す。ヨウはこのプロジェクトの初期からアドバイザーを務めてくれた。「モン族がアメリカに渡った経緯、ベトナム戦争下でたくさんの兵士や一般人が命を落としたことは今も極秘扱いにされています。上の世代もそれについて語ろうとはしません。あまりにも悲惨なエピソードが多いし、年長者は非常に謙虚だから」
イーストウッドが指摘するように、モンの人々は自分たちのことを民族ではなく、文化と捉えている。「彼らには独自の宗教や言語があって、仲間を家族と見なす傾向がある。モン族はベトナム戦争が終わってから、とてつもない苦労をしてきたんだ。ベトナムでは彼らを取り巻く状況が良好ではなかった。そこでルター派の教会や私設団体の尽力によって、モン族はアメリカに受け入れられることになった。多くの悲しみを耐え忍んできた人たちだから、非常にたくましい」
モン族の真の姿を伝えたかったイーストウッドは、モン族の役はモン族の俳優に演じてもらうのが筋と考えていた。ところが、全米俳優協会に登録しているプロはごくわずかしかいない。
そこでキャスティング・チームを率いるエレン・チェノウェスは一般公募を視野に入れ、同じチームのジェフリー・ミクラットとアメリア・ラッシュとともにインターネットでモン族のコミュニティを検索。いくつかの拠点に連絡をとり、カリフォルニア州フレズノ、ミネソタ州セントポール、ミシガン州ウォーレンなど全米各地でオーディション開催のチラシを配布した。「そこにたどり着くまでが大変でした」とチェノウェスは振り返る。「モン族のコミュニティを探しあて、顔を覚えてもらい、信頼を得て、ようやく出演希望者がいるかどうか確認する。通常では考えられないプロセスです。こちらの事情をすべて説明して、体当たりの交渉をしました」
モン文化のアドバイザーを務めたセドリック・リーはキャスティング・チームに手を差し伸べ、モン・コミュニティとスタッフとの架け橋になった。 「モン族の人たちが集まる場所に何度も出向きました」とリーは言う。「父の日の祝賀会とか、教会の行事とか。言葉の壁があるので、こちらのスタッフがモン族の年配者と話すときは私たちが通訳を務めました。相手が若者だと会話もスムーズでしたね。若い世代は英語を話しますから」
チェノウェスの一行が真っ先に訪ねたのは、ミネソタ州セントポールとカリフォルニア州フレズノの二大コミュニティ。そこのリーダーに話をつけ、全米に散らばるモン族の居住区で出演者を募ることになり、セントポールでの公開オーディションは一日がかりの大規模なものになった。
イーストウッド作品の噂はインターネット、新聞、口コミ、若い世代を通してモン族のコミュニティ全体に広まった。「みんな、本当に感激していました」と前出のポーラ・ヨウは振り返る。「あのクリント・イーストウッドの映画ということで、どんなかたちでもいいから協力したいと言う人がたくさん現われました。小さな子供から若い人たち、おじいちゃん、おばあちゃんまで集まってくれたんです。誰もが、我がモン族にチャンスを与えてくれたクリントに感謝していました」
各地で何十回となく行われたオーディションの模様はすべてテープに収められた。「オーディションのあとはロサンゼルスに引き返して、クリントも交えてすべてのテープをチェックしました」とキャスティングのチェノウェスは説明する。「編集室でテープを見ながら、候補者を絞る。各役の候補を数人まで絞り込み、最後はクリントの一存に任せました」
 数百名の応募者からメイン・キャラクターのタオ役に選ばれたのが、ミネソタ州セントポールに住む16歳のビー・バンだ。チェノウェスが語る。「私のアシスタントのアメリアがある学校を訪れた際、校内でビー・バンを見かけて声をかけたんです。私も彼の応募写真にハートマークをつけました。とにかく顔立ちが気に入ったんです。演技の経験はほとんどないけれど、ビー・バンの表情には素直で優しい人柄がにじみ出ている。どうしても出演してほしくて、合格した旨を電話で伝えたら、ビー・バンはしばし言葉を失っていました。きっと自分が選ばれるとは夢にも思わなかったんでしょうね」
数百名の応募者からメイン・キャラクターのタオ役に選ばれたのが、ミネソタ州セントポールに住む16歳のビー・バンだ。チェノウェスが語る。「私のアシスタントのアメリアがある学校を訪れた際、校内でビー・バンを見かけて声をかけたんです。私も彼の応募写真にハートマークをつけました。とにかく顔立ちが気に入ったんです。演技の経験はほとんどないけれど、ビー・バンの表情には素直で優しい人柄がにじみ出ている。どうしても出演してほしくて、合格した旨を電話で伝えたら、ビー・バンはしばし言葉を失っていました。きっと自分が選ばれるとは夢にも思わなかったんでしょうね」
ビー・バンの身長は約1m67㎝だが、ウォルト役のイーストウッドは1m90㎝近くある。並んで立つと差は歴然。「タオは文字どおり、いつもウォルトを見上げているんだ」とビー・バンは笑う。カリフォルニア州フレズノで生まれたビー・バンはミネソタ州ツインシティズで非公開のオーディションにのぞんだ。タオ役に選ばれたと知ったときは「思わずひざまづいて泣いてしまったよ。まさに天地がひっくり返る出来事だったから。夢を見ているような気分だった」とか。
撮影が始まり、最初は緊張しきりだったビー・バンもイーストウッドのスタイルにすぐに慣れたという。「イーストウッド監督のことは西部劇や『ダーティハリー』で小さいころから見てきたよ。まさか会えるとは思っていなかったのに、その人が目の前にいるんだからね。信じられなかった」とビー・バンは明かす。「監督は自然な演技、リアルな演技を好むんだ。そういうスタイルはすばらしいと思う。普段の監督は本当にいい人で、とても謙虚。監督をはじめスタッフのみなさんと過ごした時間は楽しかった。一生忘れないよ」
16歳のアーニー・ハーも多くの候補を押しのけ、スー役を射止めた。ハーをオーディションに誘ったのは前出のアメリア・ラッシュ。その日ラッシュはデトロイトで開かれたモン族の催しでブースを設置し、“映画出演者募集”の大きな看板を掲げた。「そこへアーニーが家族と一緒に通りかかった。アメリアは彼女に駆け寄り、腕をつかまえて『映画のオーディションを受けてみない?』と言ったそうです」とキャスティング主任のチェノウェスが言う。
自信とユーモアにあふれるハーは、タオの姉スー役に適任だ。チェノウェスが続ける。「私たちがイメージしたスーは“たくましいお姉さん”。弱虫の弟をかばう気持ちが強いんですが、アーニーはそんなスー像にぴったり。はつらつとしているところも魅力でした」
スーがウォルトの心にすんなり入っていったように、ハーもまたイーストウッド監督とすぐに打ち解けることができた。おかげで初めての大役も自信をもって演じられたという。「クリントはいつもリラックスさせてくれるの。うるさいことは何も言わないし、私が演じたいように演じさせてくれるし、ダメなところはきちんと指摘してくれる。こんなに偉大な監督と組めて、本当に幸せだったわ」
「ビーとアーニーの演技が自然に見えるとしたら、それはふたりに才能があるからだよ」とイーストウッドは謙遜する。「監督の力量と言いたいところだけれど、見当ちがいだね」
タオとスーの母親でシングルマザーのビューを演じるのがブルック・ジアー・タオだ。ラオス生まれの彼女はカリフォルニア州ビセイリアに移住。演技の経験はなく、オーディションには子供の付き添いでやって来たにすぎなかった。「たまたま会場に来たブルックにオーディションを受けるよう勧めたんです。そうしたらみごと合格しました」とアドバイザーのセドリック・リーは話す。「不思議なことに、ブルック本人は完璧にアメリカナイズされているんですが、母親を演じるときは別人のようになるんです」
 そんなジアー・タオにとって、本作はモン族を知ってもらう絶好のチャンスとなった。「この映画に描かれていることがすべてではないけれど、モン族の一端を垣間見てもらえると思います」とジアー・タオ。「モン族に対するみなさんの見方が変われば嬉しいし、私たちの姿やベトナム戦争で果たした役割も知ってほしい。私の父も14歳の若さでベトナムに出兵しました」
そんなジアー・タオにとって、本作はモン族を知ってもらう絶好のチャンスとなった。「この映画に描かれていることがすべてではないけれど、モン族の一端を垣間見てもらえると思います」とジアー・タオ。「モン族に対するみなさんの見方が変われば嬉しいし、私たちの姿やベトナム戦争で果たした役割も知ってほしい。私の父も14歳の若さでベトナムに出兵しました」
61歳のチー・タオはラオスに生まれ、現在はミネソタ州セントポールで暮らす。作中ではタオの祖母を演じた。「タオのおばあちゃんはモン族の言葉しか話しません。それだけにキャスティングは楽しくもあり、悩ましくもありました」とキャスティング・チームのジェフリー・ミクラットは説明する。「この役はいかにキャラが立つかがポイント。とてもユニークなおばあちゃんですが、その役にチーは適任でした」
チー・タオはイーストウッドと意気投合し、孫娘を通訳に立ててイーストウッドと話し込むことがよくあった。自身も悲劇の歴史を生き抜いてきた彼女は、全身全霊をかけてこの役に取り組んだ。「チー・タオは言っていました。『この役は私自身だから、何の苦もなく入っていける』と。彼女もこの映画で描かれているような苦境を乗り越えてきた。だから、何の問題もなくカメラの前に立つことができたのでしょう」とミクラットは言う。「じつはモン語のセリフはほとんど台本に書かれていなかったんです。ですからチー・タオのセリフもほぼアドリブ。それでも彼女はみごとにやってのけました。自分の思いや体験をセリフに込めたんです」
タオの一家を困らせる不良グループの少年たちには5人の若者が扮している。5人とも同じモン族だが、氏族も現住所もバラバラだ。「彼らには独特の存在感があって、味のある顔をしていました」とミクラットは感心する。「ニューヨークでドゥーア・ムーアを、セントポールでソニー・ビューに会ったとき、このふたりならスパイダーとスモーキーにぴったりだと思いました。ドゥーアのほうはモン族のキャストのなかでは数少ない演技経験者。彼なら、なんらかの役に合格すると思いました」
タイで生まれ、ミネソタ州で育ったムーアは俳優をめざして18歳でニューヨークへ渡った。作中ではタオとスーのいとこにあたる自称スパイダー(本名フォン)を好演している。「この映画で俳優になる夢がかなったよ」とムーア。「セットにいられるだけで、ありがたかった。クリントは最高の監督さ。本当に穏やかな人なんだ」
一方、スモーキー役を得た19歳のソニー・ビューはカリフォルニア州に生まれ、現在はミネソタ州セントポールに住んでいる。演技の経験はなかったが、そのたたずまいはスモーキーそのもの。キャスティング・チームはオーディション会場に入ってきたビューに、さっそく目を留めた。「受付の女の人と話していたら、アメリア(・ラッシュ)がいきなり現われて、『スモーキー役を受けてみない?』と声をかけてきた」とビューは振り返る。「で、受けてみたら合格したんだ」
同じく不良少年を演じているのが、オハイオ州トレード出身のリー・モン・バン、セントポール出身のジェリー・リー、そしてウィスコンシン州ミルウォーキーからやって来たエルビス・タオだ。エルビス・タオはヒップホップ系ユニットRARE(レア)に所属。RAREの曲は本作の挿入歌に採用された。
このほか重要な役どころと言えば、聖職者のヤノビッチである。まじめなヤノビッチはカトリック教の神父で、今は亡きウォルトの妻の遺志をかなえるため、ウォルトとコミュニケーションを取ろうと必死になる。
 ヤノビッチに扮するクリストファー・カーリーはイーストウッドが思い描いたイメージにぴったりはまったようだ。「彼をひと目見たとき、神父そのものだと思いました」とキャスティング主任のチェノウェスは話す。「アイルランド系の顔立ちに赤い髪。有力な候補だと思ったので、クリントにオーディションのビデオを見せたんです。そうしたら『スペンサー・トレイシーの若いころに似ているね』と言っていました。そのとき、これで決まったなと思いましたよ。もともとクリントは、この役に大物俳優を起用することは考えていなかったようです。むしろ、そうでない俳優にチャンスを与えたかったのでしょう」
ヤノビッチに扮するクリストファー・カーリーはイーストウッドが思い描いたイメージにぴったりはまったようだ。「彼をひと目見たとき、神父そのものだと思いました」とキャスティング主任のチェノウェスは話す。「アイルランド系の顔立ちに赤い髪。有力な候補だと思ったので、クリントにオーディションのビデオを見せたんです。そうしたら『スペンサー・トレイシーの若いころに似ているね』と言っていました。そのとき、これで決まったなと思いましたよ。もともとクリントは、この役に大物俳優を起用することは考えていなかったようです。むしろ、そうでない俳優にチャンスを与えたかったのでしょう」
「チャンスを与えるのが好きななんだ」とイーストウッドは語る。「新人には機会があったらどんどん出てきてほしい。とは言え、作品や役に合っているかどうかも重要な要素。名の知れた俳優がこの役にふさわしいと思えば起用するし、無名な俳優でも適任だと思えば起用する。一定のルールはない。作品ごとに、つくりも中身も変わるからね」
イーストウッドに対するカーリーの評価もほかのキャストとほぼ同じだ。「クリントは非常に物静かで、いつも淡々としている。そしてキャストとの間に大きな信頼関係を築いてくれるんだ。だから僕も安心してセットに入れるよ。自分なりの役づくりや演技を伸び伸びと試すことができる。型にはめられるような、窮屈な思いをしなくてすむんだ」
ほかのキャストとして、床屋の主人のマーティンをジョン・キャロル・リンチが演じている。マーティンは常連客のウォルトとスラングの応酬を展開するが、タオを一人前にすべく助っ人となる。また、ウォルトの長男ミッチをブライアン・ヘイリー、ミッチの妻カレンをジェラルディン・ヒューズ、ウォルトの次男スティーブをブライアン・ハウがそれぞれ好演。ウォルトの旧友で建設現場の監督ウィリアム・ヒルにはティム・ケネディが扮し、タオの将来に道筋をつけるひとりとなる。
もうひとつのメインキャスト、フォード車のグラン・トリノはスタッフがユタ州バーナルで見つけた実物だ。車両部のラリー・ステリングが説明する。「我々はのっけからツイていました。ちゃんと動く一台に出会えましたからね。あのグラン・トリノはメンテナンスが行き届いていて、クリントも大いに気に入っていました。多少は手を入れましたが、バンパーを交換した程度で、少々ツヤも出しました。色味もいいし、車内もきれい、おまけによく走るんです」
スタッフはその一台を買い取り、ミシガン州のロケ現場へと輸送。無事に出番を終えたグラン・トリノだったが、そこで話は終わらない。「撮影がすんだらミシガンで下取りに出すつもりだったが、時間が経つにつれて愛着がわいてきてしまった」と製作のローレンツは明かす。「クリントに相談したら、手放すのはやめようと言われたよ。我々のためにがんばってくれた車だから、しばらくは手元に置こうと思う」
自動車の都市でカメラは回る
 脚本では当初、ミネソタ州ミネアポリスがストーリーの舞台となっていた。しかし、ウォルトには自動車工として50年のキャリアがある。そこでイーストウッドは撮影拠点を“モーター・シティ(自動車の都市)”ことミシガン州デトロイトに置き、ロイヤルオーク、ウォーレン、グロースポイントといった住宅地で撮影を行った。また、ウォルトが暮らす町にはかつて自動車産業で栄えたハイランドパークを使った。
脚本では当初、ミネソタ州ミネアポリスがストーリーの舞台となっていた。しかし、ウォルトには自動車工として50年のキャリアがある。そこでイーストウッドは撮影拠点を“モーター・シティ(自動車の都市)”ことミシガン州デトロイトに置き、ロイヤルオーク、ウォーレン、グロースポイントといった住宅地で撮影を行った。また、ウォルトが暮らす町にはかつて自動車産業で栄えたハイランドパークを使った。
「ハイランドパークもすっかり様変わりしたよ」とイーストウッド。「昔は自動車産業の一大ベッドタウンだったんだ。全盛期には住民のだれもが自動車づくりに関わっていた。今の生産工場はかつてほどの活気はないけれど、新たに越してきた人たちもすっかり町になじんでいる。ハイランドパークにも苦しい時期はあったけれど、今も善良な市民がたくさん暮らしている」
製作のローレンツは言う。「ハイランドパークにはセットを建設したり、ロケをしたりで数週間滞在したけど、できるだけ迷惑をかけないように気をつけた。お世話になった地元の人はみんな歓迎してくれたよ」
イーストウッド作品の質と効率を上げているのは、イーストウッドからスタッフへ広がる敬意と結束の輪だろう。現場でのイーストウッドは声を上げることも、「アクション!」のかけ声も発することもなく、常に沈着冷静だ。「クリントは今の自分に満足しきっているんだと思う」と撮影のトム・スターンは指摘する。スターンが撮影監督としてイーストウッド作品に参加するのはこれで7回目。照明技師として参加した回数はそれ以上にのぼる。「クリントは今回の撮影が始まる前に『私もいい歳になったが、これが今の自分だ』なんて話していたよ」
だが、その年齢と経験がイーストウッドを無二の映画人にしているのだろう。彼ならではのアプローチとスタッフ間の連携プレーによって、イーストウッド組は撮影を手際よくこなす。
本作ではトム・スターン以下、なじみのスタッフが再結集。衣装のデボラ・ホッパー、編集のジョエル・コックス、美術のジェイムズ・J・ムラカミも常連スタッフだ。ムラカミは美術の巨匠ヘンリー・バムステッドのもとでイーストウッド作品に参加し、イーストウッドの前監督作『チェンジリング』(08)で美術デザイナーとして独立した。
「この顔ぶれは以心伝心の仲だから、段取りの説明もほとんど要らないんだ」とイーストウッドが明かす。「余計な相談や打ち合わせをいかに省くかが、現場でのテーマ。撮影中は十分に議論を尽くすけれど、議論が過ぎてややこしくなってもいけないからね。僕は奇をてらったり、マジックを使うのが好きなほうじゃないんだ。そうするのであれば、ごくさりげなくやるべきだと思う。基本的にはスタッフ全員がいい仕事をして、持ち場で力を発揮してくれればいい。映画づくりは楽しいものだよ。楽しいと感じなくなったら、引退するよ」
本作は製作のロバート・ローレンツにとって7本目のイーストウッド作品にあたる。イーストウッドとローレンツのコラボレーションについて、同じく製作を担当するビル・ガーバーが語る。「クリントにとってロバートはまたとないパートナーだよ。3人でロケハンに出かけたことがあるが、ロバートが前もって選んでおいたロケーションに対して、クリントはほとんど何も言わない。それだけロバートはクリントの意向をわかっているんだ。ふたりは名コンビだし、イーストウッド組はチームワークが抜群。連係プレーの妙だね」
ローレンツがコメントする。「クリントは古いタイプの映画人。昔ながらの手法を大切にしているのはその良さを知り尽くしているからで、それだけキャリアがあるということ。でも一方では新しいテクノロジーも積極的に採り入れて、研究、前進、向上心を欠かさない。それがクリントの原動力。そんなクリントだからこそ、一緒に仕事をしていてこんなに楽しいんだよ」
イーストウッドが発案した“神器”のなかに特製のビデオ・モニターがある。ワイヤレスなので持ち運びが自由。自ら出演するシーンを監督するときは特に威力を発揮する。「これを使うと、目を細めてカメラを覗かなくても、撮影中のシーンをリアルタイムで確認できる。離れたところからでも撮影の様子を確認できるのもありがたい」
作中で重要な役目を果たすオープンセットと言えば、ウォルトの家とその隣りのタオの家。ロケーション・チームと美術デザイナーはロケハンを重ねた結果、すべての条件をクリアする、並び建つ二件を探しあてた。製作のローレンツが振り返る。「我々がイメージしたウォルトの住まいは、家主が生涯をかけて手入れしてきたような家。近隣にあるほかの家屋はすべて時代づかせることにした。ウォルトの近所がいかに荒れているかを表現したかったんだ。主役の二軒については美術のジェイムズ(・ムラカミ)がすでにデザインを仕上げていた。なので、美術チームもセット・デコレーターのゲイリー・フェティスもすぐに作業にかかることができたんだ。下見に来たクリントは、それぞれの家の中を一周して、「気に入った。もう何もいじらなくていい」と。それくらいパーフェクトな出来栄えだったよ」
 美術デザイナーのムラカミはタオの家をデザインするにあたって写真を参考にし、モン族の住まいを実際に訪ねたという。「専門のアドバイザーに完成したタオの家を見せたら、とても感心していた。どこもかしこもリアルにできていたからね」と製作のローレンツが胸を張る。「手直しが必要なところは多少あったが、それでも全体としては『おみごと!』とお墨付きをもらったんだ」
美術デザイナーのムラカミはタオの家をデザインするにあたって写真を参考にし、モン族の住まいを実際に訪ねたという。「専門のアドバイザーに完成したタオの家を見せたら、とても感心していた。どこもかしこもリアルにできていたからね」と製作のローレンツが胸を張る。「手直しが必要なところは多少あったが、それでも全体としては『おみごと!』とお墨付きをもらったんだ」
衣装を担当したデボラ・ホッパーもネット検索に加えてモン族の祭りを見学に行き、そこにいた露天商から民族衣装についてアドバイスを受けたという。「私たちが行った先では、女性用の現代服と伝統衣装が売られていました」とホッパーは振り返る。「モン族の女性は民族衣装の作り方を母親から教わるそうなんです。スー役のアーニー・ハーは参考になるようにと、自分で縫った民族衣装を持ってきてくれました」
作中でスーとタオがモン族の礼服を着る機会は2回ある。自宅にシャーマンを招いて“魂の儀式”を行うシーン、そしてウォルトに敬意を表するシーンだ。「モン族の衣装はとても凝ったつくりになっています」とホッパーは説明する。「コインがたくさんついているのですが、コインはその一家の財力の象徴。それに、とてもカラフルなんですよ。女性はターバンを巻き、男性はベストか帯を合わせる。なんて個性的で美しいのだろうと思いました。それまで見たこともない衣装でしたから」
異文化の交流を思わせるのは全編に流れる楽曲も同じだ。自らも映画音楽を手がけるイーストウッドにとって、スコアとサウンドトラックはとりわけ重要なもの。イーストウッドの場合、撮影中にメロディを思いつくことが多いとか。「頭にメロディが浮かんだら、それをピアノで弾いて、書きとめて、あとで編曲するんだ」とイーストウッド。「誰かにお願いすることもあれば、自分でやってしまうこともある。特に決まりがあるわけではなくて、いいメロディだと思えば、それを使うまでさ」
イーストウッドが続ける。「音を入れる作業は大好きなんだ。そのころには撮影もすんでいるしね。あとは楽曲や効果音で、どうやって映像に味をつけるか。それまで50人、60人、70人のスタッフに囲まれていたのが、ひとつの部屋にパソコンを一台置いて2~3人で作業をすることになる。そういうのも楽しいものだよ」
本作の主題歌を演奏しているのは英国のジャズシンガー/ピアニストのジェイミー・カラムとドン・ランナーだ。作曲はイーストウッド、カラム、イーストウッドの実子のカイル・イーストウッド、カイルのパートナーのマイケル・スティーブンスが担当した。「4人が共同で作った曲なんだ」と製作のローレンツ。「カイルとマイケルはこの主題歌に着想を得て、残りのスコアを仕上げた」
そのスコアをレニー・ニーハウスが編曲し、録音時にはタクトも振った。ニーハウスが初めてイーストウッドと組んだのは、『タイトロープ』(84)まで遡る。
サウンドトラックにはモンとラテンのラップも数曲収録された。そのひとつは出演者のエルビス・タオが所属するラップユニットRARE(レア)の曲だ。「オーディションを受けに来た少年のなかにはラッパーが何人もいた」とローレンツ。「合格者もそうでない少年もいるが、全員がオリジナルの曲を作ってきてくれたんだ。せっかくだから、なるべく多く作中で使うことにした」
すべてのプロセスにおいて協力を惜しまなかったのがモン族のコミュニティである。そのおかげで、モン族の文化のリアルな一端を描くことができた。アドバイザーを務めてくれた人々はキャスティングのみならず、言葉、習慣、美術面での相談役を兼任。イーストウッドが雇い入れた職人たちは撮影現場で活躍してくれた。「モン族の人たちは自分もひと役買いたいと言って、本当に力を尽くしてくれた」とイーストウッドは感謝する。「一緒に仕事をすることができて光栄に思っているよ。ウォルトの目から見たモン族のストーリーに満足してもらえたら嬉しいね」
記憶に残るキャラクターを数多く演じてきたイーストウッド。今回の作品でウォルト・コワルスキーという新たな当たり役を得た。「クリントは昔からチャレンジ精神が旺盛で、同じタイプの役を演じることを好まない」とローレンツ。「そんな彼に今回の脚本はマッチしたんだ。ウォルトという役は年齢的にもイメージ的にも今のクリントにぴったり。ダーティハリー、アウトロー、妥協しない屈強な男など、今まで演じてきた役どころに通じるものもあるが、それでいて一段と深みがある。これまで以上に影のある役だが、贖罪の心を演じたことで、クリントにとっては新境地になったんじゃないかな」

ワーナー・ブラザース映画提供/ビレッジ・ロードショー・ピクチャーズ提携/
ダブル・ニッケル・エンターテイメント、マルパソ作品/原題“Gran Torino”/
監督クリント・イーストウッド/脚本ニック・シェンク/原案デイブ・ジョハンソン&ニック・シェンク/
製作クリント・イーストウッド、ロバート・ローレンツ、ビル・ガーバー/
製作総指揮ジェネット・カーン、アダム・リッチマン、ティム・ムーア、ブルース・バーマン/
出演クリント・イーストウッド、ビー・バン、アーニー・ハー、クリストファー・カーレイ、
ジョン・キャロル・リンチ、ブライアン・ヘイリー、ブライアン・ハウ、ウィリアム・ヒル/
撮影トム・スターン/美術ジェイムズ・J・ムラカミ/編集ジョエル・コックス、ゲイリー・D・ローチ/
衣装デボラ・ホッパー/音楽カイル・イーストウッド、マイケル・スティーブンス/編曲&演奏指揮レニー・ニーハウス
(c)2009 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights Reserved.
http://wwws.warnerbros.co.jp/grantorino/
2009年4月25日(土)より、丸の内ピカデリー他にて全国ロードショー
![ダーティハリー アルティメット・コレクターズ・エディション [Blu-ray]](http://images.amazon.com/images/P/B0016ZT932.09._SY160_SCLZZZZZZZ_.jpg) ダーティハリー アルティメット・コレクターズ・エディション [Blu-ray]
ダーティハリー アルティメット・コレクターズ・エディション [Blu-ray]
- 出演:クリント・イーストウッド
- ワーナー・ホーム・ビデオ
- 発売日: 2008-07-09
- おすすめ度:

- Amazon で詳細を見る
主なキャスト / スタッフ
TRACKBACK URL:

