私が、生きる肌
http://www.theskinilivein-movie.jp/2012年5月26日(土)より、
TOHOシネマズシャンテ、シネマライズ他全国ロードショー

空前絶後のオリジナリティに満ちあふれ、 カンヌ映画祭で衝撃と熱狂を呼び起こした 巨匠ペドロ・アルモドバルの新たなる冒険
 天才的な形成外科医ロベル・レガルは、神をも恐れぬ男だった。12年前に最愛の妻を失った悪夢のような出来事をきっかけに、あらゆる良心の呵責から解き放たれた彼は、倫理的に危うい遺伝子実験に没頭し、妻を救えるはずだった“完璧な肌”の研究に心血を注いできたのだ。その実験が最終段階に差しかかった頃、ロベルは監禁した“ある人物”の肉体に開発中の人工皮膚を移植し、ベラ・クルスという亡き妻そっくりの美しき女性を創り上げていくのだった……。
天才的な形成外科医ロベル・レガルは、神をも恐れぬ男だった。12年前に最愛の妻を失った悪夢のような出来事をきっかけに、あらゆる良心の呵責から解き放たれた彼は、倫理的に危うい遺伝子実験に没頭し、妻を救えるはずだった“完璧な肌”の研究に心血を注いできたのだ。その実験が最終段階に差しかかった頃、ロベルは監禁した“ある人物”の肉体に開発中の人工皮膚を移植し、ベラ・クルスという亡き妻そっくりの美しき女性を創り上げていくのだった……。
『オール・アバウト・マイ・マザー』『トーク・トゥ・ハー』『ボルベール〈帰郷〉』の“女性賛歌3部作”を始め、深遠にしてバイタリティ豊かな愛の物語を次々と世に送り出し、希代のストーリーテラーの地位を揺るぎないものとしたペドロ・アルモドバル。このスペインの巨匠が放つ『私が、生きる肌』は、昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門で上映され、そのかつて誰も観たことのないオリジナリティに満ちあふれた映像世界が、センセーショナルな衝撃と熱狂を呼び起こした最新作である。そのただならぬ興奮は全米の賞レースにも飛び火し、いよいよ多くの熱狂的なアルモドバル・ファンが待ちわびる日本への上陸を果たす。
“完璧な肌”を創る禁断実験に没頭する 天才医師と、囚われの身の美しきヒロイン あなたは、これを愛と呼べるか――
めくるめく官能と戦慄に彩られた『私が、生きる肌』は、謎めいたひとりの女性の姿とともに幕を開ける。本作のヒロインたるその女性ベラは、全裸と見まがうしなやかな肢体に肌色のボディ・ストッキングをまとい、ヨガの瞑想に耽っている。病院と研究所を兼ねた郊外の豪邸にベラを幽閉した医師ロベルは、いかなる秘密を隠し持っているのか。いったいベラは何者で、どのような宿命のもとでロベルとめぐり合ったのか。
こうした疑問を矢継ぎ早に投げかける本作は、現代から過去へとさかのぼり、まったく予測不可能な形で幾つもの驚くべき真実を提示していく。いつものようにアルモドバルが練りに練ったシナリオをベースに紡がれる物語は、スリリングにして艶めかしいミステリー・ノワールとして進行し、激しくも屈折したラブ・ストーリーへと発展。やがて観る者は、比類なきほど異様な運命をたどる主人公ロベルと囚われの美女ベラの関係に、目と心を奪われずにいられない。はたしてこれは究極の愛のみが為せる奇跡か、それとも欲望と狂気に駆られた悪魔の所業か。すべての答えは、この問題作のあまりにも数奇な全貌を見届けた観客に委ねられている。
初期作品の倒錯的なエロス&バイオレンス、先鋭的なファッション感覚を鮮やかに甦らせたアルモドバルは、それらのエッセンスを『ライブ・フレッシュ』『オール・アバウト・マイ・マザー』以降の熟成した語り口と見事に融合。さらに『顔のない眼』『フランケンシュタイン』『めまい』といった往年の名作へのシネフィル的目配せも織り交ぜ、まさしく映画作家アルモドバルの約30年に及ぶ華々しいキャリアの集大成的な作品となった。
ペドロ・アルモドバル×アントニオ・バンデラス 22年ぶりに復活した黄金コンビと 熟練スタッフが生んだ官能的な映像世界
 アルモドバルの1982年作品『セクシリア』でデビューし、スペインを代表する国際的スターへとのぼりつめたアントニオ・バンデラスが、1989年の『アタメ』以来、巨匠との久々のコラボレーションを復活させたことも大きな話題である。情熱的なラテンのセクシー男とのイメージが強い大物俳優が、愛に狂わされた異色のキャラクターを体現。ポーカーフェイスの裏に渦巻く激情を鬼気迫る存在感で伝え、観る者を終始圧倒し続ける。
アルモドバルの1982年作品『セクシリア』でデビューし、スペインを代表する国際的スターへとのぼりつめたアントニオ・バンデラスが、1989年の『アタメ』以来、巨匠との久々のコラボレーションを復活させたことも大きな話題である。情熱的なラテンのセクシー男とのイメージが強い大物俳優が、愛に狂わされた異色のキャラクターを体現。ポーカーフェイスの裏に渦巻く激情を鬼気迫る存在感で伝え、観る者を終始圧倒し続ける。
女優の魅力を輝かせることにも長けたアルモドバルが、新たなミューズに指名したのはエレナ・アナヤ。『この愛のために撃て』での妊婦姿の大熱演も記憶に新しい彼女が、本作の最も重要なモチーフである“肌”を惜しげもなく晒し、リスクを伴う難役を堂々と演じきった。そして『オール・アバウト・マイ・マザー』の名女優マリサ・パレデスが、本作の“観察者”というべきマリリアに扮し、母親の複雑な心情を表現しているのも見逃せない。
スタッフには撮影のホセ・ルイス・アルカイネ、美術のアンチョン・ゴメス、音楽のアルベルト・イグレシアスなど、アルモドバル作品の常連が集結し、鬼才ジャン=ポール・ゴルチエが衣装に参加。また本作にはフランスの作家ティエリー・ジョンケのミステリー小説「蜘蛛の微笑」という原作があり、アルモドバルの手で大胆な脚色が施され、新たな物語に生まれ変わっている。
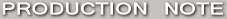
ペドロ・アルモドバル自身が語る製作ノート
囚われの美女、そして“肌”について
『私が、生きる肌』は木々に囲まれた邸宅から始まる。その家はエル・シガラルというのどかで美しい場所に立っている。石壁と高い鉄格子の門に守られた家。同じく鉄格子がついたその邸宅の窓のひとつに、動いている女性の姿が見える。その部屋の中に入ると、複雑なヨガのポーズをとる女性は裸のように見える。だが近づいていくと裸ではない。体全体が肌色のボディ・ストッキングで覆われ、まるで第二の肌のようにまとわりついている。
この最初のシーンから、エル・シガラルは自然の中の刑務所のように描かれる。孤立した場所、外部の目に触れない場所として。そのシーンに登場するのがベラである。ヨガのポーズに集中する囚われの女性。そして彼女の看守マリリアが無表情で毎日の仕事をこなしている。だがエル・シガラルの日々は、いつもそれほど平和というわけではなかった。
6年間の強制的な幽閉で、ベラはとりわけ人間の身体にとって最も重要な部分、すなわち肌を失っていた。文字通り、彼女は自分の肌を取り除かれていたのだ。
肌は他者と我々を分ける境界線である。それが我々の属す仲間を決定する。生物学的にも地理学的にも、肌が我々の感情を反映し、我々のルーツを映し出すのだ。だが肌が精神状態を反映することは多いが、肌そのものが精神というわけではない。ベラの肌は変わったが、彼女は自分自身であることを失ったわけではないのだ。このアイデンティティと、その傷つけることのできない性質が本作のもうひとつのテーマである。とにかく自分の肌を失うなど、残酷極まりないことだ! 多くの損失の中でたったひとつベラに残されたもの、それは彼女の願望によって、あるいは手術室で執刀するロベルの手によってもたらされる死である。だが彼女は生来のサバイバーだった。多くの困難ののちに、ベラは「自分の肌の内側で生きることを学ぼう」と決心する。たとえ、それがロベルに押しつけられた肌であったとしても。いったん第二の肌を受け入れたベラは、生き残るために最も大切な2番目の決断をする。「待つことを学ぼう」と。
製作中に脳裏をよぎった映画たちについて①
 ある日、カーニバルの最中にトラの衣装を着た男が、ベラが囚われている部屋の封印されたドアのところまで入り込んでくる。この出来事がエル・シガラルの3人の住人の張りつめた緊張感を破る結果になる。逆説的にカーニバルの衣装を着た人間が入った瞬間、3人は自分たちの仮面を脱ぎ去り、それによって最後の悲劇が暗い影を投げかけ始め、3人の当事者たちの誰もがそれを防ぐことができなくなるのだ。
ある日、カーニバルの最中にトラの衣装を着た男が、ベラが囚われている部屋の封印されたドアのところまで入り込んでくる。この出来事がエル・シガラルの3人の住人の張りつめた緊張感を破る結果になる。逆説的にカーニバルの衣装を着た人間が入った瞬間、3人は自分たちの仮面を脱ぎ去り、それによって最後の悲劇が暗い影を投げかけ始め、3人の当事者たちの誰もがそれを防ぐことができなくなるのだ。
こういった特徴的な物語から、私はルイス・ブニュエルやアルフレッド・ヒッチコック、そしてフリッツ・ラングのゴシックからノワールまでのすべての映画を思い起こした。さらにポップな雰囲気のハマー社のホラー映画、もっとサイケデリックで低俗な映画のジャンル“イタリアン・ジャッロ”の作品群、それにもちろん『顔のない眼』(59)でジョルジュ・フランジュが描いた叙情主義も連想した。
こういったすべてのことを参考にしたのち、私はそのどれもが、この映画で私が必要とするものに当てはまらないことに気づいた。私は数ヵ月間、真剣にフリッツ・ラングとF・W・ムルナウに対する賛辞をこめて、モノクロ画面に解説とセリフの字幕を付けたサイレント映画を作ろうかと考えていた。悩んだ末に、私は自分のやり方でいこう、そして直感に従おうと決心した。結局いつもそうなるのだが……。ジャンル映画の巨匠たちの影に脅かされることなく(といってもこの映画がどのジャンルに属するのか、私にはわからないということも理由のひとつだが)、そういった映画に対する自分の記憶を断ち切ろうとするように。
私にわかっていたのは、簡素な語り口の、雄弁で自由なビジュアルを前面に押し出さなくてはならないということだった。しかも、たくさんの血が楕円形を描いてあふれ出たとしても決して惨たらしくならないこと。撮影前にこういった前提から入るのは初めてではなかったが、この映画は特にそうすべきだと思ったのだ。
製作中に脳裏をよぎった映画たちについて②
先ほど私はこの映画を企画開発しながら思い浮かべた技術的協力者(監督)たちを忘れ、自由な道を選ぶと言ったが、だからといってこの映画がまったくの孤島だというわけではない。映画製作の過程を通じて、予期せぬ客たちが数名現れたのも事実だった。文学的で幻想的な映画のこだまが反響している。ジェームズ・ホエール監督の『フランケンシュタイン』(31)やアルフレッド・ヒッチコック監督の『めまい』(58)、『レベッカ』(40)を考えないなんて不可能だ。この映画の最初の映像には、ルイス・ブニュエル監督さえ引き合いに出した。それはトレドの街のごく普通の映像だった。そこで物語の空間と時間が決定する。エル・シガラルはトレドから4キロに位置する場所にある。その街を見せるために私はカメラを設置したが、同じ場所で40年前にブニュエルが『哀しみのトリスターナ』(70)の舞台として街の景色を撮影したことを知った。そして私はこの巨匠への賛辞として、そのショットを再現しようと思ったんだ。
おそらく最初に意識したのは、ジョルジュ・フランジュの『顔のない眼』だったと思う。その影響でフランジュの『ジュデックス』(63・未)に導かれたが、それはジャン・マレーが主演した『ファントマ』シリーズや、1960年代にマリオ・バーヴァ監督が仮面のヒーローが登場するコミックを映画化した『黄金の眼』(67)のように、時を経て移り変わってはまた思い出す作品の1本だった。黒いボディ・ストッキングに身を包み、顔はシリコンのマスクで覆われたエレナ・アナヤが、階段を必死に駆け下りてくる。エレナは私にそういう映画への子供時代の記憶を思い出させた。そこに登場した幻想的なキャラクターたちは思春期の私の一部となったが、彼らはマスクをつけ、黒いタイツを着ていたのだ。
ベラと監視画面について
 我々はあらゆるサイズのスクリーンに映し出された映像に囲まれて生活している。建物の大きな壁から、マッチ箱と同じサイズの小さな携帯電話の液晶に至るまで、さまざまな起源の映像や意図的な映像が一斉に流され、我々を攻撃してくる。
我々はあらゆるサイズのスクリーンに映し出された映像に囲まれて生活している。建物の大きな壁から、マッチ箱と同じサイズの小さな携帯電話の液晶に至るまで、さまざまな起源の映像や意図的な映像が一斉に流され、我々を攻撃してくる。
自分の家さえ安全ではない。泥棒を防ぐためにセキュリティ・カメラによって撮影されている。あるいは家庭内での出来事や夫に殴られた妻、子供たちを虐待するベビーシッター、子供たちを誘拐する人間が撮影され、あるいは撮影されていることを知らない誰かと性的な関係を持っているところを、詳しく映し出した映像を手に入れようとする人間までいるのだ。テレビのリアリティ番組は言うまでもない。隔絶して生活する家族やグループまで、カメラやスポットライトに昼も夜も囲まれている。
我々は見つめられ、見つめている。あらゆる場所にカメラがある。映像のないスクリーンは空っぽで、活性化していない死に等しい。
ベラは灰色の部屋に囚われている。その部屋にはふたつ窓があり、網目状の窓ガラスがシールドの役目を果たしている。そこには鉄格子もついている。床の色は壁より少しだけ濃い灰色で、部屋の上部の隅にふたつの監視カメラがあり、それが大きなキッチンに設置されたふたつのスクリーンに映像を流している。
キッチンに流れる映像はモノクロで、つねに部屋全体を映し出す監視補足映像である。ロベルだけが私室で見ることのできる映像はカラーで、カメラはベラの身長とほぼ同じ映像を映している。ロベルは彼女の背丈と同じ映像を楽しんだり、ズーム機能で彼女を自分のほうに引き寄せたりすることができ、その場合、ベラの顔が部屋全体に映し出される。
カメラが現代人の生活に存在するように、ベラの生活に存在している。だが彼女を囚われた動物のように見せるのと同様、フレームの中の彼女のサイズによっては、スクリーン上のベラの映像が物語に微妙で重要な情報を加えている。例えば、トラ男がキッチンのスクリーンで彼女を発見するとき、ベラはジムで使われるようなゴムボールでヨガをしている。スクリーン上の彼女のサイズは小さい。特にトラ男がフレームに入ってきて、顔をスクリーンに近づけたとき、まるで彼がベラを食べてしまうような印象を受ける。実際に彼は次のシーンでそうしようとするのだが、その力関係はキングコングのハートを射止めた金髪女性を思い出させる。
反対に、ロベルが自分の部屋に入り、中央にベッドが置かれたベラの部屋の全体像が見えるテレビのスイッチを入れたとき、我々が最初に気づくのはそのプラズマ・スクリーンの大きさである。壁の中央に置かれたそのスクリーンが、何となく透明な仕切りの役目を果たしている。
ロベルがそのスクリーンの前の長椅子に座り、ベラの映像を顔が映るだけの大きさにズームアップすると、ロベルの身体や部屋の大きさと比べてベラの顔がとてつもなく巨大に映し出される。ベラの顔がその部屋を占拠し、その部屋の住人となる。だがロベルはそれに気づかない。こういった密接した私的な監視の中で、ベラは被害者であるにもかかわらず、その不釣り合いな顔が、恍惚の表情で彼女を見つめるロベルの力よりも大きな力を放つ。この外科医を見つめているのは、彼ではなく、彼女のように見える。望みさえすれば、ロベルを貪り食うことができるのはベラなのだという印象を与えるのである。
ロベルの“顔”について
アントニオ・バンデラスに撮影前に見るように指示した映画の1本が、ジャン=ピエール・メルヴィル監督の『仁義』(70)だった。ロベルはその映画の冷淡な泥棒とは何の関係もない。私がアントニオに見せたかったのは、キャラクターたちの“無表情”だった。アラン・ドロンは、最小限の顔の表情で演じたメルヴィル監督との3本の映画で最も輝いていた。私はアントニオに、とりわけ残虐なシーンでは何の表情も見せないように頼んだ。そして『仁義』の冷淡な犯罪者たちを参考にしてもらったのだ。だがそうすることで私が見せようとしたのは、ロベルの邪悪さではなく、むしろ彼の完璧な感情の欠如だった。
精神病質者を定義するものは、彼ら自身が“他人”の立場になれないことである。だから彼らは想像を絶する残虐行為ができるのだ。他人の痛みを感じることも想像することもできない。ロベルのような精神病質者はサディストではない。彼らは痛みを引き起こすことを楽しんでいない。ただ彼らは、自分の犠牲者の痛みがどんなものかを知らないだけなのだ。

音楽:アルベルト・イグレシアス 編集:ホセ・サルセド 撮影:ホセ・ルイス・アルカイネ 衣装:ジャン=ポール・ゴルチエ
出演:アントニオ・バンデラス,エレナ・アナヤ,マリサ・パレデス,ヤン・コルネット,ロベルト・アラモ
2011年/スペイン/120分/カラー/アメリカンビスタ/ドルビーデジタル 配給:ブロードメディア・スタジオ
©Photo by José Haro Ó El Deseo http://www.theskinilivein-movie.jp/

![私が、生きる肌〔ハヤカワ・ミステリ文庫〕 [文庫]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/P/4151747524.09._SCMZZZZZZZ_.jpg)
